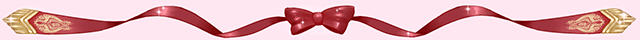
赤い糸
第14章 大切な時間
「綺麗ですね。」
広縁の一人掛けの椅子に座る京介さんの膝の上を間借りさせてもらってる私は 窓の外の夕陽色に染まる日本庭園を眺めていた。
「おまえは夕陽が好きだよな。」
背中越しに聴こえる声、腰に回わされた腕が心地よい。
「どうしてでしょうね。」
球場のバックスリーンに落ちる夕陽も京介さんのお家から眺められる夕陽も 全部同じ太陽なのに違う色をしている。
それを教えてくれたのはインドアだった私を毎週のように外へと連れ出してくれた京介さんのおかげかな。
空の蒼さや風の音も匂いも季節によってこんなにも違うことを京介さんは教えてくれた。
「…璃子。」
名前を呼ばれる度に重なる唇。
音を立てるように軽やかだったり吸い付くようで甘かったり…まるでお話ししているみたいなキス。
旅立つ前に…大好きだよって気持ちがもっと伝わるといいな。
*
「ホント、旨そうに食うな。」
頷きながら頬張るおまえについ言葉が出てしまう。
「旨そうじゃなくて美味しいんです!」
テーブルに並べられた料理はどれも手が込んでいた。
「京介さん…」
「ありがとう。じゃ、璃子も。」
「ありがとうございます。」
浴衣の袖を抑えながら徳利を差し出して酌をしてくれる。
豪華な料理がテーブルいっぱいに並べられても 俺にとって一番のツマミはおまえのその笑顔だったりする。
「もう一本付けてもらいますか?」
「いや、もういいよ。」
自然とピッチが早くなっていたようだ。テーブルには空いた徳利が4本も並んでる。
「少し飲みすぎちゃいましたかね。」
俺の相手をしてもらっているせいか璃子は首までピンク色に染めて柔らかく微笑んでいた。
「たまにはいいだろ。」
「ウフフ、そうですね。」
飲み終えた徳利を並べながらいつもよりも艶っぽい声色でそう呟く。
浴衣姿で髪をアップにしているおまえは酒の力を借りてかさらに色香を漂わせていた。
おまえはここまで思い出してるかな。
「飯食ったら風呂入るからな。」
「…はぃ。」
そう、酒が入ると積極的になるってこと。
首筋までほんのり色付くおまえの体はきっと全身ピンク色なんだろう。
「タオル禁止だからな。」
「はぃ?!」
「ダメに決まってんだろ。」
「…意地悪。」
俺はきっとその姿を見て酔うんだろうな。
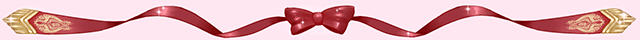
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える