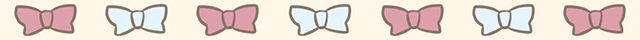
Hello
第52章 にのみみ * にのあい
ソファーにそっと横たえられる。
「……大丈夫?」
「……と、思うか?」
「だよね……」
喘ぎ続けて掠れた喉は、もうしゃべるのも辛くて。
水、と小さく言ったら、相葉さんは、ちょっと待ってねと、優しくキスしてくれた。
腰ももう限界で動けなかったから、どろどろの体を綺麗にふきあげてもらう間も、俺はマグロ状態。
でも、相葉さんは、抱くだけ抱いたら我にかえったみたいで、そこからはまるで従者のようにかいがいしく世話をしてくれた。
「飲ませてあげよか?」
「……うん」
相葉さんがボトルの蓋をあけて、水を含み、俺を抱き起こしてくれた。
あ……そこまでしてくれんだ、と思ってたら、押し当てられた唇から、あったかい水が注ぎ込まれ。
何度か繰り返したのち、甘いキスをしながら抱き締められる。
サイドテーブルにある、さっきまでつけてた猫の耳の玩具をみて、相葉さんは感慨深げに囁いた。
「……すっごく可愛かったよ、にの」
「……あたりまえだ」
「また耳つけてね」
「それは嫌」
なんでー、と、くふふっと笑う相葉さんの広い背中に手をまわし、そういえば、にゃあ、とか言っちまった気がするな、と、気恥ずかしく思いながら、温かい胸のなかで目を閉じた。
******
「ね、ね、翔ちゃん、これおすすめ」
「?なんだ、こりゃ」
「えっちのとき、松潤にさせてみて?めっちゃ可愛いから」
「……マジで?」
数日後の現場で、相葉さんと翔ちゃんのヒソヒソ話がきこえてしまった俺は、思わずパソコンの前で難しい顔をしているJをみてしまった。
あの耳の玩具を譲ろうとしてる相葉さん……ほんとろくなこと考えないんだから。
Jに、忠告したげようかな、と一瞬思ったけど……まあ、よそのカップルのことだから、いっか。
Jなら、プライドの高い血統書つきの猫に変身するんだろうな……。
そんなことを思いながら、ソファに座り直しあぐらをかいた。
隣では大野さんがスヤスヤ寝てる。
俺は音を消して、ゲームのスイッチをいれた。
もう猫にはならねーかんな。
fin.
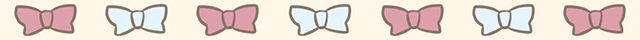
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える