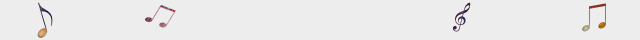
君の光になる。
第1章 プロローグ
「……十五……十六……十七……」
夕子は歩数を数えながら、白杖で点字ブロックを探りながら歩を進めた。駅のホームに上がるエスカレーターを降り、夕子の足で十九歩目の場所に彼女が乗降する場所がある。カッカッカッという点字ブロックを撫でる音が急に途絶え、トンという音に変わった。
――あ、あれ?
白杖で再び探る。トンという音……。手の感触からすると柔らかい物だ。
「あら、ゴメンなさい……」
少ししゃがれた声の感じから、夕子の今年五十五歳になる母親くらいの声色だ。品のよい声だ。
「いえ……私こそ大切な荷物……叩いちゃってすみません……」
夕子は白杖で辺りを探る。再び、トンと音が聞こえた。目新しい革の匂いだ。夕子が嗅いだことのある匂い。恐らく、学生カバンだ。
夕子は自分がどちらから来てどこに行こうとしているのか、方向を見失ってしまった。
夕子の背後の方で「チッ」と舌打ちが聞こえた。
どこからか
「見えないんなら、独りで歩かなきゃいいのに、なあ」
と言う声が聞こえる。
「まもなく、電車が参ります……」と言うアナウンスのあとに線路からの小さな振動を感じた。金属が焼けるような匂いがする。その中に微かなトニックシャンプーのような香りがした。
「あー、僕に掴まって……ください……」
若い男性のような声だ。子供ではない。爽やかなトニックシャンプーの匂い。
「え、私……ですか?」と、夕子が言い終わるまもなくトニックシャンプーの香りが近づいた。
――お父さんと同じ匂い……。
トニックシャンプーは、これが爽やかで気持ちいいのだと行っていた父親と同じ匂いだ。先日病で亡くなってしまったが……。今、夕子は電車で三十分ほどの場所にある霊園に父親の墓参りに行く途中だった。
手のひらでその匂いを探る。
肘の骨ばった感触。
身体が浮き上がるように足が進んだ。
すうっと身体が引っ張られた。でも、恐怖心はなかった。
夕子は歩数を数えながら、白杖で点字ブロックを探りながら歩を進めた。駅のホームに上がるエスカレーターを降り、夕子の足で十九歩目の場所に彼女が乗降する場所がある。カッカッカッという点字ブロックを撫でる音が急に途絶え、トンという音に変わった。
――あ、あれ?
白杖で再び探る。トンという音……。手の感触からすると柔らかい物だ。
「あら、ゴメンなさい……」
少ししゃがれた声の感じから、夕子の今年五十五歳になる母親くらいの声色だ。品のよい声だ。
「いえ……私こそ大切な荷物……叩いちゃってすみません……」
夕子は白杖で辺りを探る。再び、トンと音が聞こえた。目新しい革の匂いだ。夕子が嗅いだことのある匂い。恐らく、学生カバンだ。
夕子は自分がどちらから来てどこに行こうとしているのか、方向を見失ってしまった。
夕子の背後の方で「チッ」と舌打ちが聞こえた。
どこからか
「見えないんなら、独りで歩かなきゃいいのに、なあ」
と言う声が聞こえる。
「まもなく、電車が参ります……」と言うアナウンスのあとに線路からの小さな振動を感じた。金属が焼けるような匂いがする。その中に微かなトニックシャンプーのような香りがした。
「あー、僕に掴まって……ください……」
若い男性のような声だ。子供ではない。爽やかなトニックシャンプーの匂い。
「え、私……ですか?」と、夕子が言い終わるまもなくトニックシャンプーの香りが近づいた。
――お父さんと同じ匂い……。
トニックシャンプーは、これが爽やかで気持ちいいのだと行っていた父親と同じ匂いだ。先日病で亡くなってしまったが……。今、夕子は電車で三十分ほどの場所にある霊園に父親の墓参りに行く途中だった。
手のひらでその匂いを探る。
肘の骨ばった感触。
身体が浮き上がるように足が進んだ。
すうっと身体が引っ張られた。でも、恐怖心はなかった。
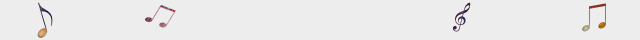
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える