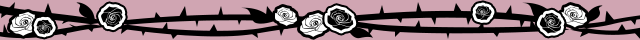
アクセサリー
第2章 最強タッグ
そういって神崎さんは左足にクリームを塗った手をすぅっとすべらせマッサージを始めた。
意識が朦朧としてきて、左足の太ももまでマッサージされたのは覚えているけど、気がついたら神崎さんの手は背中に移動していた
今度は右の方から、さわやかなベルガモットとローズマリーを混ぜたような爽やかで元気づけられるような軽やかな匂いがしてきた。
不思議と心が高揚してきて、さっきまでの眠さや
気だるさは飛んでいった。
と思っていたら、また睡魔に襲われた。
やはり神崎さんのハンドテクニックには敵わなかった。
遠くで神崎さんの声が聞こえた
「七海様、仰向けになってください。」
目を開けるのもやっとだった私は神崎さんの力をかりながらなんとか仰向けになり、また目を閉じた。
次に目が覚めると今度はあたりから、むわぁっと色っぽい匂いがした。
この匂いは嫌でも女という事を自覚させられるような、なんとも色っぽい香りだった。
色っぽくて華やかで気品ある自立した大人の女性しか付けてはいけないようなそんな香りだった
なんだか私の中の女濃度が1段、2段上がった気がした
「七海様、終了ですよ」
「ありがとうございました。なんか今香っている匂い?大人の女って感じでどきどきしちゃいました」
「ふふ、七海様にぴったりですよ。今夜はその意気ですよ♪」
私はドキッして固まってしまった
「ふふふ、想像されました?七海様正直ですね」
「ちょっともう神崎さん~辞めてくださいよ~」
「堕天使のくせに両手を頬に当てるんじゃないわよ、そんなのお世辞に決まっているでしょう」
一足先に終わたそうちゃんがこちらに来ていた。
ちっ折角浸っていたのに見られてしまった
「堕はいらないわよ。天使。そして神崎さんはお世辞は言わないのよ」
「あんたってハッピーな脳みそね。その思考回路私にも分けてほしいわ」
そういってバスローブ姿でソーサーとティーカップを持ったそうちゃんはスタスタとリビングテーブルに向かって歩いていった
「神崎さん?そうちゃんのあの格好にソーサーとティーカップ持ってるだけで十分ハッピーな脳みそ持ってるって言えるよね?」
神崎さんがクスクス笑っていた。
「ビッチ風情が何をいけしゃーしゃーと。このソーサーをフリスビーにしてあんたの部屋に投げ込むわよ。」
意識が朦朧としてきて、左足の太ももまでマッサージされたのは覚えているけど、気がついたら神崎さんの手は背中に移動していた
今度は右の方から、さわやかなベルガモットとローズマリーを混ぜたような爽やかで元気づけられるような軽やかな匂いがしてきた。
不思議と心が高揚してきて、さっきまでの眠さや
気だるさは飛んでいった。
と思っていたら、また睡魔に襲われた。
やはり神崎さんのハンドテクニックには敵わなかった。
遠くで神崎さんの声が聞こえた
「七海様、仰向けになってください。」
目を開けるのもやっとだった私は神崎さんの力をかりながらなんとか仰向けになり、また目を閉じた。
次に目が覚めると今度はあたりから、むわぁっと色っぽい匂いがした。
この匂いは嫌でも女という事を自覚させられるような、なんとも色っぽい香りだった。
色っぽくて華やかで気品ある自立した大人の女性しか付けてはいけないようなそんな香りだった
なんだか私の中の女濃度が1段、2段上がった気がした
「七海様、終了ですよ」
「ありがとうございました。なんか今香っている匂い?大人の女って感じでどきどきしちゃいました」
「ふふ、七海様にぴったりですよ。今夜はその意気ですよ♪」
私はドキッして固まってしまった
「ふふふ、想像されました?七海様正直ですね」
「ちょっともう神崎さん~辞めてくださいよ~」
「堕天使のくせに両手を頬に当てるんじゃないわよ、そんなのお世辞に決まっているでしょう」
一足先に終わたそうちゃんがこちらに来ていた。
ちっ折角浸っていたのに見られてしまった
「堕はいらないわよ。天使。そして神崎さんはお世辞は言わないのよ」
「あんたってハッピーな脳みそね。その思考回路私にも分けてほしいわ」
そういってバスローブ姿でソーサーとティーカップを持ったそうちゃんはスタスタとリビングテーブルに向かって歩いていった
「神崎さん?そうちゃんのあの格好にソーサーとティーカップ持ってるだけで十分ハッピーな脳みそ持ってるって言えるよね?」
神崎さんがクスクス笑っていた。
「ビッチ風情が何をいけしゃーしゃーと。このソーサーをフリスビーにしてあんたの部屋に投げ込むわよ。」
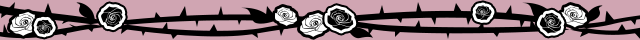
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える