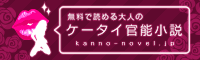七瀬からの補足
第15章 "14章 一瞬の交差
P288
大野さん視点で宮様と桃木殿が着ている服の説明です
奈良時代から平安時代に貴族等の身分が高い者が着る服(下記に集めます)
大野さんには、その服の名前や着方を知ってる設定です。
着た事もある(笑)
文官束帯(ぶんかんそくたい)
武官束帯(ぶかんそくたい)
平安時代の貴族の正装。
朝廷の行事などに着用される。
笏を持ち、平緒・下襲の裾を後ろに長く引く。
飾り太刀を持つ。
着方が大変複雑で、やがて簡略化した衣冠が生まれる。
衣冠(いかん)
束帯を簡略にしたもの。文武官の区別もなく、
宮中での勤務服として広く用いられた。
袴の代わりに指貫をはき、笏の代わりに檜扇を持つ
冠 直衣(かんむりのうし)
烏帽子直衣(えぼしのうし)
貴族が自宅でくつろぐ時に着用した。
狩 衣(かりぎぬ)
狩りや蹴鞠など野外の遊び着
半尻(はんじり)
上級公家 (摂家,清華) の子息に用いられた装束の一種。
童子用の狩衣 (かりぎぬ) に類するもので,後身の裾 (尻) が前身の裾より短く,身幅もやや細い。前張 (まえばり) という袴と合せて使用した。
水干(すいかん)
狩衣に似て盤領(丸えり)の一つ身(背縫いがない)仕立てである。
ただし襟は蜻蛉で止めず、襟の背中心にあたる部分と襟の上前の端につけられた紐で結んで止める。
大野さん視点で宮様と桃木殿が着ている服の説明です
奈良時代から平安時代に貴族等の身分が高い者が着る服(下記に集めます)
大野さんには、その服の名前や着方を知ってる設定です。
着た事もある(笑)
文官束帯(ぶんかんそくたい)
武官束帯(ぶかんそくたい)
平安時代の貴族の正装。
朝廷の行事などに着用される。
笏を持ち、平緒・下襲の裾を後ろに長く引く。
飾り太刀を持つ。
着方が大変複雑で、やがて簡略化した衣冠が生まれる。
衣冠(いかん)
束帯を簡略にしたもの。文武官の区別もなく、
宮中での勤務服として広く用いられた。
袴の代わりに指貫をはき、笏の代わりに檜扇を持つ
冠 直衣(かんむりのうし)
烏帽子直衣(えぼしのうし)
貴族が自宅でくつろぐ時に着用した。
狩 衣(かりぎぬ)
狩りや蹴鞠など野外の遊び着
半尻(はんじり)
上級公家 (摂家,清華) の子息に用いられた装束の一種。
童子用の狩衣 (かりぎぬ) に類するもので,後身の裾 (尻) が前身の裾より短く,身幅もやや細い。前張 (まえばり) という袴と合せて使用した。
水干(すいかん)
狩衣に似て盤領(丸えり)の一つ身(背縫いがない)仕立てである。
ただし襟は蜻蛉で止めず、襟の背中心にあたる部分と襟の上前の端につけられた紐で結んで止める。

 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える