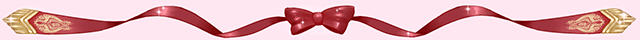
キラキラ
第31章 イチオクノ愛
Aiba
楽屋の扉をしめて、大きく伸びをした。
もう何年もやっているバラエティーの収録 は、大先輩のタレントさんを長に、非常にアットホームな空気のなかでやっていて、とても心地よい。
共演してるタレントさんもいい人ばかりだし、適度な緊張感も求められて、勉強することも実際多かった。
ここで培った経験は、嵐のレギュラー番組などの収録にも、役立っていると思うし、自分の持っている番組にも何かしらよい影響をもらっているだろうと思う。
「んしょ……」
トレードマークのオーバーオールを脱いで、私服のジーンズに履き替える。
今日は、動物の赤ちゃんの紹介があったから、子犬も子猫もたくさん抱っこした。
脱いだ服に、キラキラの細い毛がついてるのは、そいつらのものだろう。
「かわいかったなー……」
独りごちて、手のひらに残る温もりを思い出した。
信じられないほど小さくて柔らかくて、ちょっとの刺激でどうにかなってしまいそうな愛らしい生命。
赤ちゃんは、一人でなにもできないからこそ、その可愛さで、周りに助けをもらってるんだ、と聞いたことがある。
ペットを飼うのは、仕事上無理なのは分かってるけど、あんな可愛らしい姿に触れると、もともとの動物好きの血が騒ぐよね。
Tシャツに腕を通しながら、メンバーで一番子犬に近いやつの顔を、ふと思い浮かべた。
茶色い潤んだ瞳は、いつも澄んでいて、笑ったときに細められるそれは、抱き締めたくなるほど可愛らしくて。
もういい年したオッサンつかまえて、可愛いもないだろうよ、と苦笑いされるけど、俺にとって、にのはいつまでも可愛い恋人だ。
「あー……なんか、すっげ会いたくなってきた!」
呟いて、スマホを鞄から出して手に取った。
《会いたい。会える?》
アプリを開き、テレビ局にいることを伝えたら、にのは、偶然同じ建物で、もうすぐ打ち合わせらしくすぐに返事がかえってきた。
《これから打ち合わせだから、もう少しかかるけど》
《待ってる!》
《動物園の楽屋にいる?》
《そう》
《んじゃ、終わったらそっち行くわ。待ってて》
《わかった!》
いつものやり取り。
もうすぐ彼に会えることを、嬉しく思いながら、俺はソファーに寝そべって、読みかけの雑誌を開いた。
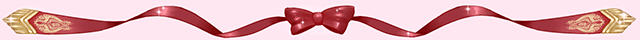
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える