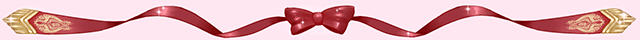
赤い糸
第3章 ネックレス
「明日?」
「そう、明日は美紀とお出掛けするんだ。」
その角を曲がれば私の家はもうすぐ。
「どこに遊びに行くの?」
「あのね、美紀の彼氏がやってる野球チームの応援に行くの。」
達也さんはお仕事なので、暇をもて余す私は美紀と野球の応援に行くことになっていた。
「野球か…」
「ダメ…?」
溜め息混じりに呟いた達也さん。
美紀の彼氏が在籍しているとはいえ 野球チームと言えば男の人ばっかり。
やっぱり快く送り出してはくれないよね…
私も反対の立場だったら首を縦に振る自信はない。
でも、達也さんはニコリと微笑むと
「たまには太陽の下で過ごすのもいいんじゃないか?」
なんてサラッと言える大人だったりする。
「いいの?」
行ってもいいか聞いたのは私なのに…
「いいに決まってんだろ。楽しんでこい。」
「うん!」
この懐の深さに私は甘えていた。
「野球か…楽しそうだな。」
そんな彼が好きだった。
*
「じゃ、明日は暖かくしていくんだぞ。風邪引いたら月曜日に頑張って働いてもらえないからな。」
「わかってますぅ!」
達也さんはいつものように私の頭にポンと手を置くと
「じゃあな。お疲れ。」
「お疲れ様でした。」
私は車のドアを開ける。
そして
「バイバイ…」
…バタンっ
彼の車が見えなくなるまで手を振りながら見送った。
…今日もナシか
車を乗っているときも何故だか右手がいつもソワソワする。
そのソワソワした感じが気持ち悪くて私はいつもバックか自分の左手を握りしめている。
そして…唇に違和感が宿る。
真冬の乾いた風のせいで潤いが乏しい唇を撫でる。
彼と最後にキスをしたのはいつだっただろう。
もう かなり前だと思う。
…でも、覚えてる。彼の唇は夏でも冬でも冷たいんだ。
そして私の心を満たして骨抜きにされてしまう。
「痛っ!!」
コメカミに立っていられないほどの激痛が走る。
私はその場にしゃがみこみ大きく深呼吸しながらこの痛みが逃げるのを待つ。
きっと達也さんはまだ本調子じゃない私に気を使ってくれているんだ。
…私と違って大人だもんな。
ハートのネックレスに指を掛けもう一度深呼吸する。
風に曝されたネックレスはあの唇のように冷たかった。
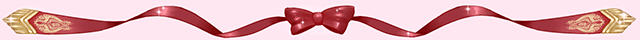
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える