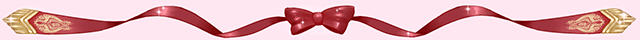
赤い糸
第3章 ネックレス
どうしてだろう…
京介さんは私と視線が合うように膝を付き合わししゃがみこんでくれていた。
どこか寂しそうで悲しそうな瞳で…
だからかな、その瞳で見られると視線を外せなくなる。
目をギュッと瞑って視線を外そうともするけど…
ほらね…瞼を開ければ今度はスゴく優しい瞳をする。
その視線が何故だかとても心地よくて私まで頬が緩んでしまうんだけど
その反面 何もかもを見透かされているように思えてしまう。
…あ、この香り
そして帽子を被せられたときにも感じた心が暖かくなる香り。
これは汗の匂いなの?それとも香水?
まるで私の心をギュッと鷲掴みにされてるかのよう。
紡がれる言葉も掠れた声も、ベンチから指示を出していたあの大きな声も同じだった。
不思議と彼に接すると全部包み込まれているように錯覚した。
でもね…一つだけ苦手なものがあった。
それはその大きな手。
私よりも一回りも二回りも大きな手が触れようとすると私の頭は一気に痛くなる。
病室でもそうだった。
「約束ね」と差し出された小指に何故か異常に反応してしまい割れるんじゃないかと思うほどの頭痛が襲う。
さっきもそう。彼に髪を撫でられたら心地よさの反面まるで電気が走ったみたいに頭の奥がズキズキと痛みだした。
でもね、不思議なんだけどそれがスゴく悲しいんだ。
こんなこと達也さんには言えないけど 撫でてもらうのが心地よかったから。
もっと触れてって…ねだってしまいそうなほど彼の大きな手は私の心を揺さぶった。
「ん?あぁ…すごいマメだろ?」
じっと見すぎてしまったかな。
「あ…いや…スミマセン…」
信金さん…いや、京介さんは私の目の前に大きな手を広げる。
「小学生の頃から野球ばっかりやってたから見ての通りマメだらけなんだ。」
「小学生からなんですか?」
「そう、兄貴の影響で。」
「痛く…ないんですか?」
「もう痛くはないよ。」
彼は手を何度かグーパーしてヒラヒラと振った。
「本当ですか?」
「俺はウソはつかないよ。」
私は今 自分の身に起こっている二つのことに驚いていた。
それはいつの間にか京介さんと普通にお話しできてることと
「こんなにマメだらけなのにですか?」
「だから…俺は璃子ちゃんに絶対ウソはつかない。」
この手に触れたいって衝動と戦っている自分に…
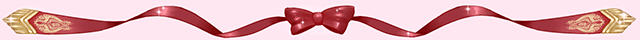
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える