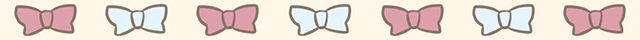
ペンを置いた日
第2章 初めての気持ち
「嘘つき」
少女の言葉が、男の胸に刺さる。
嘘つき、嘘つき、嘘つき。
ずきずきと、男の胸を締めつける。
「出て行ってください、あなたみたいな人、私は知りません」
男は、抵抗もしないまま、部屋を出た。
家も出、駅近くの公園のベンチに腰掛け、天を仰いでいた。
自分の過去と決別しようとした、諦めた夢を忘れようとした結果が、今の衰退した男の姿である。
漫画なんて嫌い、そう思うことでしか、過去を切り離せない。そんな弱い自分に、自然と溜息が出た。
溜息と同時に視線を下げると、男の目の前には妹が立っていた。
心配そうな顔で、男の顔を覗き込んでいる。
「どうしたんだお兄ちゃん、落ちてるガムでも食べたのか?」
心配そうにしている妹に、男は先の出来事を話してみることにした。
「なるほど、なるほど」
妹は頷く。
自分の描いたキャラクターが自分の前に現れたなんて話を信じてもらうことができないどころか、精神異常でも起こしたのではないかと思われるやもしれない。
しかし妹は、やはりなにかを察したように、笑った。
「お兄ちゃんはその子のこと、大事に思ってるんだね。だから、傷つけてしまったから、そうして困っていたんだね。それと--」
と、妹は一瞬言葉を詰まらせ、そして、
「おっと、これはいいか」
と話を打ち切った。
「とりあえずお兄ちゃん、自分の気持ちを正直に伝えた方がいいと思うよ。くよくよなよなよ悩んでいないで、夢はもう諦めたって、きっぱり」
「--彼女を傷つけてあげればいいと思うよ」
少女の言葉が、男の胸に刺さる。
嘘つき、嘘つき、嘘つき。
ずきずきと、男の胸を締めつける。
「出て行ってください、あなたみたいな人、私は知りません」
男は、抵抗もしないまま、部屋を出た。
家も出、駅近くの公園のベンチに腰掛け、天を仰いでいた。
自分の過去と決別しようとした、諦めた夢を忘れようとした結果が、今の衰退した男の姿である。
漫画なんて嫌い、そう思うことでしか、過去を切り離せない。そんな弱い自分に、自然と溜息が出た。
溜息と同時に視線を下げると、男の目の前には妹が立っていた。
心配そうな顔で、男の顔を覗き込んでいる。
「どうしたんだお兄ちゃん、落ちてるガムでも食べたのか?」
心配そうにしている妹に、男は先の出来事を話してみることにした。
「なるほど、なるほど」
妹は頷く。
自分の描いたキャラクターが自分の前に現れたなんて話を信じてもらうことができないどころか、精神異常でも起こしたのではないかと思われるやもしれない。
しかし妹は、やはりなにかを察したように、笑った。
「お兄ちゃんはその子のこと、大事に思ってるんだね。だから、傷つけてしまったから、そうして困っていたんだね。それと--」
と、妹は一瞬言葉を詰まらせ、そして、
「おっと、これはいいか」
と話を打ち切った。
「とりあえずお兄ちゃん、自分の気持ちを正直に伝えた方がいいと思うよ。くよくよなよなよ悩んでいないで、夢はもう諦めたって、きっぱり」
「--彼女を傷つけてあげればいいと思うよ」
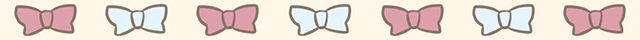
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える