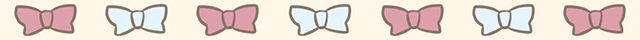
Hello
第42章 from jealousy * バンビズ
Jun
顔馴染みになったコンシェルジュにペコリと礼をして、俯いたまま脇をすり抜け、足早にエレベーターに乗り込んだ。
ゆっくり閉まった扉により、完全な個室状態になったことに安堵し、はぁっと息を吐き出した。
悪いことをしてるわけでもないのに、関係が関係なだけに、妙に用心深くなってしまう。
メディアの前でのように、堂々としてればいいのに、プライベートになったとたん、そんな自分が
保てないでいた。
あの人のテリトリーに入ると、特にそれが顕著。
俺は、ウィーンという小さな機械音とともに、加算されてゆくデジタルの数字をじっと見あげた。
都心にある、このタワーマンションの高層階に、あの人の部屋はある。
連絡があると……俺がここにくる。
……決して彼がうちに来ることはないのだ。
チクリとした胸の痛みには気がつかない振りをして、腕時計に目をおとすと、時刻は、まだ宵の口だった。
ずいぶん早く仕事終わったんだな……。
あの人から連絡をもらったら、友達といようが、食事してようが、飲んでようが、何をおいても最優先なのは、暗黙の了解。
そうしないと、後々大変なことになるのは身をもって知ってる。
スケジュールは、がっつり把握されてるから、仕事だったから気がつかなかった、という言い訳は通用しないのだ。
つまり会いたいタイミングはいつもあの人が握ってる。
俺だって、会いたくないわけじゃない。
むしろ、ずっと一緒にいたい。
でも……。
軽い浮遊感とともに目的の階についたことで、俺はため息をつき、モヤモヤしそうな心に蓋をした。
コツコツという足音を響かせ、フロアの一番奥の重厚な扉の前で立ち止まる。
「……」
与えられてる合鍵を使って、静かに扉を開ける。
とたん、ふわりと香るのは、あの人が好むディフューザーのそれだ。
男の一人暮らしのくせに、意外とそういうことにはこだわっていて、リビングや寝室、全部香りが違う。
あるとき、片付け、苦手なくせに、と突っ込んだら、苦手だからこそだ、と言い返されたっけ。
長い廊下を歩き、つきあたりの扉を開けば、最小限の灯りしかともってない、広いリビング。
皮の真っ黒なソファーに座った彼は、悠然と微笑んで。
「……遅かったな」
と、言った。
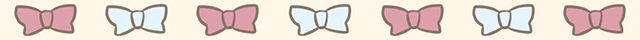
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える