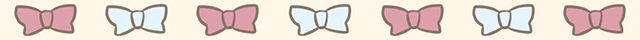
Hello
第36章 Never mind * バンビズ
Sho
……疲れた。
さすがに、タフだと周りに言わしめる俺も疲れた。
キャスターの仕事を終え、テレビ局から自宅までの僅かな時間ですら意識を手放してしまうほど、体は休息を求めていて。
「櫻井さん……着きましたよ?」
「……え、もう……?」
マネージャーの遠慮がちな声に、意識を戻せば、すでに自宅に到着してることに驚愕した。
さっき、目をつぶった、と思ったけど。
深い深い眠りに落ちていたことを思いしる。
「……大丈夫ですか」
「ああ……うん。大丈夫」
「明日は、一時に迎えに来ます」
「分かった……おまえも早く休めよ」
俺と同じように動いてるマネージャーも、くたくたのはずだった。
労う言葉をかけてやったら、彼もクマのできた目元を細めて、はい、と笑った。
「……ただいま」
一番奥のリビングに明かりが灯っていることを確認する。
途中、扉のあいたままの寝室を覗けば、人の気配がないことに、ため息をつく。
あいつ……まだ起きてんのか?
大丈夫なのかよ。
カチャリとリビングの扉をあければ、エアコンのきいた暖かい部屋がむかえてくれて、寒さに固まっていた体が、ホッとした。
と、同時に、ブランケットにくるまってカウチに横たわる潤をみつけ、眉をひそめてしまう。
色白の顔は、微妙に赤く染まっていて。
浅い呼吸を繰り返す彼に、ああ……やっぱダメだったか、と、もう一度ため息をついた。
「潤……おい。潤」
丸まった肩をゆすれば、潤んだ大きな瞳がぼんやりとあいた。
「……翔……くん」
「しんどいのか。病院行ったのか」
「……ううん……」
気だるく首をふる潤の額に手をおいた。
東京で早くから仕事があった俺は、潤と会うのは名古屋で別れて丸1日ぶり。
ライブ後半から体調面に不安を持ってた潤だが、気合いで乗り切ったところまでは見届けた。
だけど、実は結構限界に近かったことを俺は知ってる。
マネージャーに無理矢理予定をねじ曲げさせて、
今日の夕方から明日の午前中まで休みをぶっこんだってきいたけど。
「薬は」
「飲んだよ……朝より全然マシ」
「そっか」
「……それより、翔くんも長丁場お疲れ様……」
「おう。疲れたわ、さすがに」
潤の手がのびてきて、俺の頬に触れる。
その熱い指に、彼の今の状態を知る。
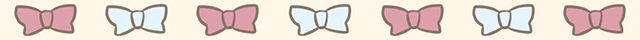
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える