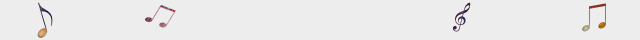
君の光になる。
第6章 ある月曜日
――遅くなっちゃった。
そこは普段の雑踏が想像できないくらいに静かだった。
「楽しかったです。私、時間を忘れていました」と、夕子は笑って見せた。
「立花さんの家まで送ります。だけど、この季節ハロウィンの飾りがキレイです」
「どんな感じですか? ハロウィンの飾りって……」
「ええ、ここのは一面紫色の電飾の中にカボチャの茶色が散りばめてあって、キラキラと幻想的です」
頭のキャンバスにそのイメージを描いた。夕子は子供のときから耳で聞いた事柄を想像するのが好きだった。
「私、少し車から降りてもいいですか?」
しばらくすると車のドアが静かに開いた。子供のころ、母親が読んでくれた童話の中のカボチャの馬車から降りるようだ。
夕子は大きく深呼吸した。冷たい風が髪を撫でる。昼間のような騒々しさはなかった。
「立花さん……」
そこは普段の雑踏が想像できないくらいに静かだった。
「楽しかったです。私、時間を忘れていました」と、夕子は笑って見せた。
「立花さんの家まで送ります。だけど、この季節ハロウィンの飾りがキレイです」
「どんな感じですか? ハロウィンの飾りって……」
「ええ、ここのは一面紫色の電飾の中にカボチャの茶色が散りばめてあって、キラキラと幻想的です」
頭のキャンバスにそのイメージを描いた。夕子は子供のときから耳で聞いた事柄を想像するのが好きだった。
「私、少し車から降りてもいいですか?」
しばらくすると車のドアが静かに開いた。子供のころ、母親が読んでくれた童話の中のカボチャの馬車から降りるようだ。
夕子は大きく深呼吸した。冷たい風が髪を撫でる。昼間のような騒々しさはなかった。
「立花さん……」
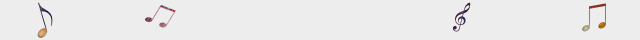
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える