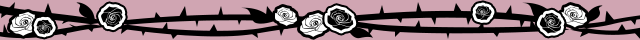
アクセサリー
第2章 最強タッグ
私はウォーターサーバーまでゆっくり
歩いていって横目でテキパキ料理を作っている
そうちゃんを盗み見した。
おネェだなんて知らなかったら
きっと惚れてしまうかも…
そうちゃんの横顔は日本人離れしたすっとした
鼻とふと深めの堀。目は大きいのだけれど
どちらかというと横に大きい。
そうちゃんの流し目は私でもドキッとしてしまう
そんな事を考えてたら
コップから水が溢れでてた
「やーよ、七海ったら。朝からやらしい事考えてたんじゃないのぉ〜もぉ〜」
「…そうちゃんの顔について考察してただけよ」
「はぁい?なに人の顔考察してんのよ。あとでレポート10枚褒め言葉で埋め尽くしなさいよ」
そうちゃんはそういって鼻歌を歌いながら
料理に集中し始めた。
私は組んだお水を持ってソファにゆっくり座った。
がしゃん、という音でびっくりした私は
うたた寝していた事に気付いて目をこすりながら
ダイニングテーブルに目を向けた。
「わっわぁ〜凄い、凄いよぉ!!」
そうちゃんは誇らしげな顔をしながら座っていた。
テーブルは写真集にでも出てきそうなほど
華やかで、テーブルには花が置かれていたり
食器もコップもスープン、ナイフ全てが
洗練されていた。
「朝から気分がいいわぁ♡私ってやっぱり天才」
「うんうん、本当こうゆう所天才だよ」
「やだ、照れるってば♡」
「てゆか、うちにこんな食器あったんだ」
「あんた料理しなさ過ぎて見た事ないだけでしょ」
「私の家なのに、そうちゃんの方が詳しいよね」
「あったり前じゃないの〜ここのマンションうちが…」
「えっ?」
黙るそうちゃん。
「え?もしかして、そうちゃんのパパの?」
「さ、さ、ご飯食べましょうよ♡夜の予定の為に元気やる気つけなきゃよ♡」
「そうちゃん…話題のすり替え方、ヘタクソ」
「しばくぞオラ」
にこっとエセ妖精が笑った。
「あ、はい。いただきます」
そうちゃんはなぜだか家の仕事について
話す事が嫌みたい。いつもは何も言わないけど
たまーに機嫌がいいと言いそうになる。
言いそうになって言わない。
だからいつも気になるけど
聞いたらヤバイ雰囲気だから聞けない。
はぁ…ご飯食べよ
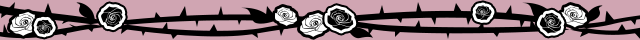
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える