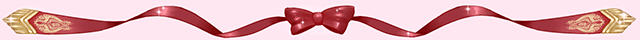
キラキラ
第5章 hungry
ストレッチが終わり、ダッシュのメニューをこなしているときに、二人はやってきた。
井ノ原先輩に気がついた部員が次々に大きな声で挨拶をしている。
俺も、周りに続いて頭をさげて顔をあげると、ニコニコする井ノ原先輩と微笑む大野さんが目に入った。
思わずこちらも、笑顔になる。
雅紀が、ダッシュを中断させようと声をあげかけて、井ノ原先輩に制止されてた。
「いいよ、続けて」って口の動きで分かる。
基礎体力をつけるこのダッシュメニューは、バスケ部に古くから受け継がれてる、実に地味で、実に辛い練習のひとつだ。
バスケは、体力面で大きな負荷がかかるスポーツだから、この延々と続く体力勝負的なメニューは、毎日かかさない。
俺は流れる汗を手の甲でぬぐい、雅紀のかけ声とともに、全力でダッシュした。
練習が始まって二時間が経過しても、二人はまだいた。
……ってか、井ノ原先輩はともかくとして、大野さんは、つまらないんじゃないかな?と逆に心配になる。
人の良さそうな顔してるから、俺帰るねって、言えないんじゃねえかな。
速攻の練習をしながら、チラリと視線をおくると、楽しそうに談笑しながら、こちらを見てる二人。
……ひょっとしてバスケ経験者かな?
余計なことを考えてたら、シュートを外してしまった。
あ。
雅紀が、怖い顔して俺を見た。
集中しろって、目が言ってる、
やべ。
「もう一本!」
俺は、声をあげた。
「お疲れさまでした!」
全員で、ミーティング後、練習終了。
時刻は午後7時ジャスト。
結局、井ノ原先輩たちは、30分ほど前に俺らに目配せして帰っていった。
ちょうど試合形式が終わる頃だったから、雅紀が全員集めようとしたけど、「いい、いい」と井ノ原先輩は笑って、オッケーサインをしていった。
「はー……疲れた」
汗と、食べ物の匂いと、男臭さが入り交じった部室内の一番奥の特等席で、雅紀がメロンパンをかじりながらためいきをついた。
「やっぱり、ずっと見てられると緊張感が違うよな」
俺もクリームパンの袋をあけながら苦笑い。
練習を見守る目は、やはりどこか厳しく感じる。
優しいけど、怒ったらほんと怖い先輩だったからなあ。
「相葉先輩、あのキレーな人誰だったんですかー?」
スポドリを手に、なつっこい笑顔を浮かべて近づいてきたのは、一年生の二宮。
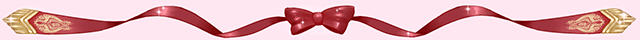
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える