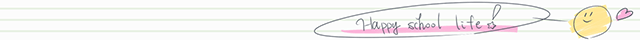
原稿用紙でラブレター
第5章 青いハートに御用心
「…はい、では終わります」
その合図で号令を出した学級委員に続いて挨拶が響く教室。
直後に騒がしくなったかと思えば教壇のにのちゃんはすぐに教室から出て行き。
一番後ろで見学をしていた俺は慌てて後ろのドアから出てその背中を追い掛けた。
何だか懐かしい光景。
そういえば昔もこんな風に授業が終わったらすぐに出て行くにのちゃんを追い掛けてたっけ。
「待って、にの…みや先生!」
その声に肩を揺らして振り返ったにのちゃんは、ハッとしたように目を開いて俺を見た。
すぐに追い付いて駆け寄ったら申し訳なさそうに眉を下げてこちらを窺う瞳。
「ごめん、忘れてました…」
「いや全然!てかやっぱすごいね、授業。すっごく勉強になっちゃった」
「いや…別にあんなの普通です。相葉先生も慣れればできますよ」
「いや~俺はまだ全然…」
頭をポリと掻いてヘラッと笑いつつ、ジッとこちらを見上げるにのちゃんの視線に気付いて。
「…どうしました?」
「いやっ、別に…」
気を付けて敬語で問い掛けたら急に耳を赤くしてふいっと目を逸らしてしまったにのちゃんに疑問符が浮かぶ。
そのまま廊下をペタペタと歩いていくのを追い掛けて隣に並んだ。
「…どうしたの?」
「…なんでもない」
顔を屈めて小声で聞いてもほんのり赤い耳のふちは益々染まっていくだけ。
「にの…」
「後で言いますっ…」
そうして足早に階段を降りて行った背中をぼんやり見つめて。
なんだ?
どうしたの?にのちゃん…
待ってよ、俺また何かしたっけ…?
この手のパターンは今まで何度も経験済み。
お互い思ってることは何でも言い合うっていうのが俺たちが一番大事にしているルール。
けどたまにこうやってにのちゃんのガードが急に堅くなる時があるんだ。
そんな時は大抵俺に理由があって。
ぐるぐると頭の中を巡らせるけど全然思い当たる節がない。
首を捻りながらとぼとぼと階段を降りていると、最後の一段に足を掛けたところで思いがけない衝撃がきた。
「うおっ!」
どんっとぶつかってきた体を慌てて支えれば、顔を上げたのは驚いた目で俺を見る小柄な生徒で。
「ぁ…すみませんっ!」
真っ赤な顔でぺこりと頭を下げ、逃げるように階段を駆け上がっていった。
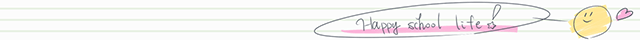
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える