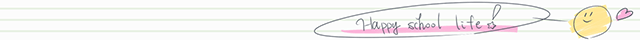
原稿用紙でラブレター
第5章 青いハートに御用心
押された体勢のまま後ろに手をついてヘラヘラと笑うその顔にも更にイライラが募り。
無言でテーブルの上のマグカップを両手に持ってキッチンへと立った。
シンクにバシャッと流したコーヒーが飛び散り、気持ちと相まって苛立ちを抑えられない。
「…にのちゃーん?どうしたの?」
背中に受ける間延びした声は反省の色なんかまるで無くて。
動かない俺に何度も呼び掛けてくる間もふつふつと。
思えば相葉くんと付き合ってからケンカらしいケンカは一度だってしたことがない。
そもそも俺の方がずっと年上だからそういう感情にすらならなかったんだけど。
相葉くんも成人して、こうして大人への階段を一歩ずつ確実に歩み始めてる。
加えて今は俺と同じ職場に居て同僚とまではいかないけど立ち位置は一緒。
高校生の頃からすると随分と大人になったなって思うところはあるにしても、まだまだ子どもっぽい部分もたくさんあって。
そういうところが相葉くんらしくて好きなんだけど…
でも、それってもしかして俺が甘やかしすぎなのかな。
この先社会人として一人前になんなきゃいけない相葉くんをいつまでも俺が子ども扱いしてちゃダメだよね。
そうだよ、俺がしっかりしなきゃなんだ。
…相葉くんの為にも。
「ねぇにのちゃん、晩ご飯どうする?俺も手伝う、」
「帰って」
「えっ?」
「…今日はもう帰って」
シンクの縁を掴んで振り向かずに告げた。
このままなかったことにしちゃダメだ。
ちゃんと線引かなきゃ…俺の為にも。
「なんで?にのちゃん…怒ってんの?」
「…怒ってるよ」
「え、なに?もしかしてやっぱやきもち、」
「っ、違うってば!いいから今日は帰って!」
振り返って反論すれば慌てたように立ち上がってキッチンへ駆けてくる姿。
「なに?ごめんにのちゃん、俺分かんないから教えて」
「真面目に聞いてくれない人には何言っても一緒です。
…じゃあね、また明日」
詰め寄る相葉くんをくるっと反転させて背中を押し遣る。
「ちょっ、にのちゃん!」
床に置いていたカバンを拾い上げて振り向いた胸にぐいっと押し付けて。
縋るように見つめてくる戸惑った瞳に一瞬揺らぎそうになったけど、最後は目を合わせずに玄関のドアをパタンと閉めた。
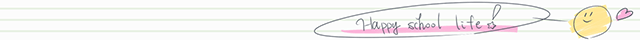
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える