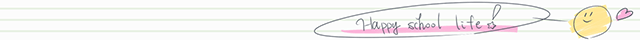
原稿用紙でラブレター
第5章 青いハートに御用心
体育館の地下にある用具庫。
高校の頃は一度も立ち入ったことのなかったこの場所に、放課後にのちゃんと二人きり。
こもった空気や特有の用具の匂いに顔を顰めつつ、ずらりと並んだ備品の中からリストと照らし合わせながらチェックをしていく。
「ディスクマーカー…」
「あ、あった」
しんと静まり返った室内に俺とにのちゃんの小さな呟きだけが響く。
今日の授業も特別これといって会話を交わすこともなくて。
今朝のにのちゃんの様子が気になってはいたけど、放課後にちゃんと話せるからと信じて声を掛けるのをグッと堪えたんだ。
「…じゃあビブスが各色あるか確認しましょうか」
「ぁ…はい」
棚に収められた番号付きのビブスの枚数を数えることになり、にのちゃんと隣り合って並ぶ。
黙々と手を動かす右隣の気配。
チラッと視線を遣ればメガネを掛けた綺麗な横顔。
今朝は腫れていた瞼ももう隠す必要もないくらいいつも通りに戻っていた。
にのちゃん…ごめんね。
俺が空回りしてあんなこと言っちゃったばっかりに。
でもさ、ほんとに俺心配なんだよ。
あの時ははっきりにのちゃんが恋人ですって生徒に宣言したワケじゃないけど。
なんかああでもしなきゃ俺…
俺自身がちゃんと立っていられないような気がして。
にのちゃんは俺の大事な恋人なんだ。
絶対誰にも渡すつもりなんかないんだから。
「…にのちゃん、」
「……」
「あ、二宮先生…」
「……」
「ねぇせんせ、」
「ちょっと数えてます今!」
急に発せられたその声に思わず肩を揺らしてしまった。
隣を見れば眉間に皺を寄せて睨んでくるメガネの奥の揺れる瞳。
「…すみません」
「仕事してください早く」
そう言ってふいっと目を逸らし再び手を動かし始めた。
ことごとく些細なことで怒られてしまう学習出来ない俺。
心の中で深く溜息を吐いてビブスに手を掛けようとした時、隣からごくごく小さな声が聞こえてきて。
「昨日…」
「…え?」
その声に顔を向けると、目を伏せたままきゅっと唇を噛み締めた横顔があった。
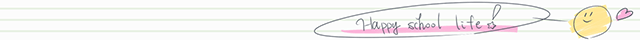
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える