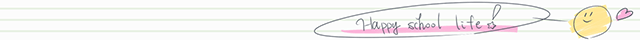
原稿用紙でラブレター
第3章 消費期限は本日中
向かいから度々聞こえてくる"超おいしい!"という嬉々とした言葉に、ようやく肩の力が抜けていく。
自分以外の誰かに料理を食べて貰うことがこんなに緊張するなんて初めて知った。
ましてや、好きな人に初めて料理を振る舞う場面なんてなかなか経験できるものじゃない。
とりあえず第一段階はクリア…かな。
目の前で瞳を輝かせながら料理を頬張っていく相葉くんを盗み見て、ふと松本先生のプランが頭を過ぎる。
"ムードが大事"と念を押されつつ告げられた数々の指令。
そのどれもが今までやったこともなければ、勿論やってもらったことすらなくて。
俺にはハードルが高過ぎることばかりを提案されたけど、松本先生が『相葉は絶対こういうの好きだから』と自信満々に言うから。
相葉くんの何を知ってんの?って少し不審に思ったけど、俺にはもうその言葉を信じるしか道はないんだ。
「ねぇ食べないの?」
ふいに聞こえた声に顔を上げれば、同じくこちらを見る頬いっぱいに料理を詰め込んだ相葉くんと目が合い。
その口元に目が行き、ハッとして息を呑みこんだ。
よ、よしっ…
「ついてる…」
ゆっくりと左手を伸ばした先の、口角についた炒飯の米粒をそっと摘まんで。
おずおずと自分の口に持っていき、目は伏せたままその指を唇の隙間に押し込んだ。
…今ので、大丈夫?
ドキドキしながらチラッと目を上げると、さっきの状態で固まったまま動かない相葉くん。
その反応に一気に焦燥感に駆られて。
えっうそ、引かれた…?
「あ、ごめんねっ勝手に…」
「いやっ!あ、ありがと…」
遮るように被せられた言葉と赤くなった相葉くんの顔に、少なからず引かれてはいなかったとホッと一安心する。
はー…心臓に悪い。
ムード作るのってこんなに大変なの?
どこまでが良くてどこからがダメなのか、もう全然分かんないよ…
俺…
ちゃんとできるのかな…?
また料理を食べだした相葉くんに気付かれないように、こっそりと小さく溜息を吐いた。
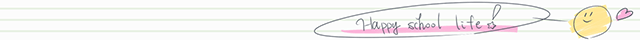
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える