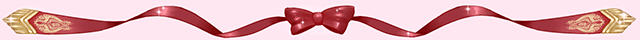
赤い糸
第9章 想い
もしかして…とか、だったらいいなって
「お願いです…離してください。」
ずっと思ってた。
でも、現実にそうだと知ると
「…璃子。」
何も覚えていない自分に嫌気が差す。
抱きしめられた瞬間に感じたのは紛れもない“愛”だった。
私はこの人に大切にしてもらってたんだと思う。
「好きだよ。」
声色や息遣い、ぬくもりがそう思わせた。
でも、何にも覚えていない私は胸に廻されている腕に触れることも出来ない。
「ゴメンナサイ…」
だって私はあなたに心惹かれ始めていたけど
「本当に…思い出せないんです。」
あなたとの大切な日々をすべて忘れてしまっている。
京介さんは私の体から少し離れるとクルリと向き直らせ
「いいんだ。璃子は思い出せなくても…」
いつものように私と視線を合わせるように屈み込んで
「俺はおまえとの日々を全部覚えてる。」
私の心を落ち着かせてくれる。
「なら、教えて下さい…私たちのこと。」
*
京介さんに促されて並んだ椅子に膝を付き合わせるように座り両手を繋ぐ。
確か、記憶喪失だと告げられたあのときも川野先生に手を擦られてた。
でも、京介さんは違う。
まるで私に寄り添うように視線を合わせ
「俺の一目惚れだったんだ。」
誰も話してくれなかった私たちのことを話し始めてくれた。
「おまえなかなかOKしてくれなくて…すげぇ困ったんだぞ。」
一つ一つのエピソードを
「おまえが初めて作ってくれた料理はカレーと璃子特製の人参ドレッシングがかかったサラダ。」
京介さんは微笑みながら私に話してくれる。
「そのハートのネックレスは野球に付き合わしてばかりのお詫びと感謝の意味を込めてクリスマスにプレゼントしたんだ。…言っとくけど女にアクセサリーをプレゼントしたのは璃子が初めてだからな。」
その笑顔を見ていたら
「これはその時おまえがくれたネクタイピン。俺のお守りだな。」
私もこの人のことを愛していたんだと思い知らされた。
でも、何を聞いても私の頭の中はおろか
「…ゴメンナサイ。」
無数に張り巡らされているどの細胞もあなたを思い出してはくれない。
「そか…」
それでも笑っていてくれるあなたの後ろから
「璃子ちゃん、少し休憩しようか。」
コーヒーの香りと共に現れたのは彼と同じように優しく微笑んだ夏樹さんだった。
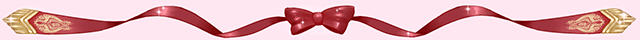
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える