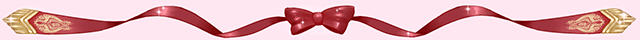
赤い糸
第10章 壁
「おいで…」
食器を片付けたあとふと気付いた。
私はこの部屋に入ってからずっと動き回っていたと
「…はぃ。」
だから急にやることがなくなった私はどこで何をしたらいいのかわからずキッチンの前に立っていた。
そこで差し出された長い手に引き込まれるようにして座ったのが
「ありがとうな。」
彼が座っている少し固いソファーだった。
…どうしよう
京介さんは私の髪に触れると指でクルクルと弄り
「もっと傍に…」
そのまま彼の胸へ抱き寄せた。
手を膝の上でギュッと握りフーフーと小さく深呼吸してカチコチに固まってしまった体を解きほぐすように目を瞑る。
「璃子の匂いだ。」
きっとこんなときはお腹の辺りに腕を回して逞しい胸に頬を寄せるのが正解なんだろうけど
「クサいですか?」
微かに感じることができる彼の吐息を意識してしまうと、全身が固まってしまった私は動くどころか頷くことも出来ない。
「バーカ、んなわけねぇだろ。」
記憶を無くしてしまった私でもわかることだってある。
「すげぇいい匂い。」
男と女がひとつ屋根の下で…いや、ソファーに並んで座って抱き寄せられれば
「…璃子。」
それはもう唇やらなんやらを重ねるものなのだろうと
「いつまで下向いてんだよ。」
それが世界基準なんだということぐらいはわかってるつもりだ。
「ほら、こっち向いてごらん。」
彼の吐息が私の髪にかかると弄んでいた指先が私の頬をとらえ
「ちゃんと顔見せて。」
スッと上を向かされた。
近すぎて視点が定まらずぼんやりと見える彼の瞳
「なぁ…ダメ?」
掠れた声で囁かれると長い指先が私の唇をなぞる。
この間はまだ心の準備が出来ていなくて彼のことを押し退けてしまったけど
「璃子…」
汗を握りしめている私の手を彼のマメだらけな手が優しく包む。
「キスしていい?」
京介さんにとっては久しぶりのキスだろうけど
「…。」
今の私にとってははじめてのキス。
答える代わりに目を閉じると柔らかな感触が私の唇を包み込んだ。
…あ
彼の唇は私の心をじんわりとあたたかくするのに
…冷たい。
忘れなかった…忘れられなかったこの感覚。
「好きだ。」
ずっと待っていた冷たい唇の持ち主は
「大好きだ。」
愛したことすら思い出せない京介さんのものだった。
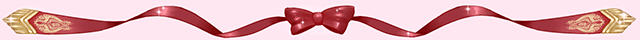
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える