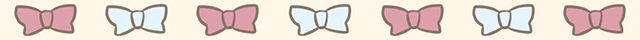
ペンを置いた日
第2章 初めての気持ち
「しかし、結果は良いものではありませんでした。何度か持ち込みに行った編集部からダメだしを受け、また一からのものになってしまいました。しかし、あなたは諦めませんでした。何度ダメだしを受けてもめげず、何度賞を落ちたとしても挫けませんでした」
「.........」
「漫画家になるんだと心を強く持ち、それでも挫けそうな時は家族を思って頑張りました。しかしあなたは三年前、突然ペンを置いてしまいました。それは初めて漫画を描いた日と同じ、そして今日と同じ八月六日のことです」
「.........」
「最後の応募にしようと心に決めた漫画が、落選したのが理由でした。才能がないのだと、部屋で涙を流しながら呟いていました」
「.........それが、どうした」
男は部屋の端へと辿り着いた少女に視線を向けて、言った。
正直に言ってしまえば、漫画家になる夢を諦めきれているわけではない。未練がましくなりたいと思っている。
だからこそ、男は自分が嫌いになる。
「あなたは、まだ漫画を描きたいはずです。でなければあんな表情、あんな悲しそうな表情はしなかったはずです。何度か賞に選ばれたことだってあったじゃないですか。一位ではありませんでしたけれど、確実に、賞をもらったことがあったじゃないですか。そんな人が、才能がないわけがない」
「...僕に才能なんてないよ、今は脳すらあるか怪しい」
男は微笑してみせる。
「いえ、あります。脳細胞も、才能も」
「それに、僕は言ったはずだ、漫画なんてバカみたいなもの嫌いだって」
「いえ、そんなはずはありません。あなたは言っていました、漫画を描くことは楽しいって、心の底から楽しいって、死んでも描き続けたいと。自分を偽らないでください」
どうか、正気を保ってください。
そう言い少女は男に抱きついた。
部屋の端から端までを走り、勢いよく、抱きついた。男の胸に顔をうずめて少女は涙を流す。
必死に声を我慢しながら、涙を零した。
「.........」
「漫画家になるんだと心を強く持ち、それでも挫けそうな時は家族を思って頑張りました。しかしあなたは三年前、突然ペンを置いてしまいました。それは初めて漫画を描いた日と同じ、そして今日と同じ八月六日のことです」
「.........」
「最後の応募にしようと心に決めた漫画が、落選したのが理由でした。才能がないのだと、部屋で涙を流しながら呟いていました」
「.........それが、どうした」
男は部屋の端へと辿り着いた少女に視線を向けて、言った。
正直に言ってしまえば、漫画家になる夢を諦めきれているわけではない。未練がましくなりたいと思っている。
だからこそ、男は自分が嫌いになる。
「あなたは、まだ漫画を描きたいはずです。でなければあんな表情、あんな悲しそうな表情はしなかったはずです。何度か賞に選ばれたことだってあったじゃないですか。一位ではありませんでしたけれど、確実に、賞をもらったことがあったじゃないですか。そんな人が、才能がないわけがない」
「...僕に才能なんてないよ、今は脳すらあるか怪しい」
男は微笑してみせる。
「いえ、あります。脳細胞も、才能も」
「それに、僕は言ったはずだ、漫画なんてバカみたいなもの嫌いだって」
「いえ、そんなはずはありません。あなたは言っていました、漫画を描くことは楽しいって、心の底から楽しいって、死んでも描き続けたいと。自分を偽らないでください」
どうか、正気を保ってください。
そう言い少女は男に抱きついた。
部屋の端から端までを走り、勢いよく、抱きついた。男の胸に顔をうずめて少女は涙を流す。
必死に声を我慢しながら、涙を零した。
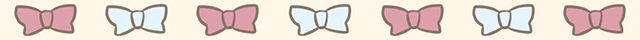
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える