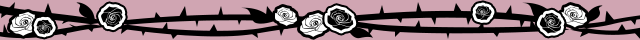
子供じゃない…上司に大人にされ溺愛されてます
第7章 愛され過ぎて
江藤彩音side
目頭が熱くなり、頭の中で嵐が吹き荒れる。
営業部に入って、自分のデスクの上を片付けて、帰る支度をして、
鞄を持って、家に帰ろうとして、入り口で思い切り、誰かにぶつかった。
「…うっ、…あっ、ごめん…っ」
顔を見られたくないから、俯いたまま、すぐに帰ろうと通り過ぎようとして、
その誰かに腕を掴まれた。
「…どうしたんですか?江藤さん?」
振り返って、そこに居たのは桐生だった。
メガネの奥の瞳が、心配そうに光る。
「……何でもない、目に…ゴミが入っただけ」
我ながらベタな言い訳だと思い、涙をグイッと拭う。
「…ああ、そんなにしたら、余計に痛みますよ?」
あたしの言葉に真面目に反応して、頬を優しく包むようにして、
上を向かされた。
「…ちょっと何するの?」
「だから目のゴミを取ってあげますから、上を向いて下さい」
…しょうがないから上を向く。
至近距離でじっと瞳の奥まで覗かれて、恥ずかしくて緊張してしまう。
「下を向いて、…視線だけ動かすんですよ?横も向いて、左右にゆっくりです」
じっくり眼球を覗かれてしまい、
「もういいから、離してよっ」
堪えられずに桐生の腕を掴んだ。
「…ゴミはないみたいですけど、やはり何かありましたね?…教えて下さい、あなたのことは全て知りたいんです」
「……いいから離してよっ」
桐生はゴミはないと気付いてる癖に、変わらずに至近距離でじっと見つめられる。
あたしの頬に触れる手が熱い。
「教えてくれないと離しませんよ?」
カッとなってますます暴れるあたしを、桐生はぎゅっと抱きしめた。
びっくりして顔を上げるあたしの目の前で、桐生の顔が斜めに傾く。
ゆっくりスローモーションのように、唇が重なって、眼鏡とぶつからないと、
ぼんやりと思った。
「こうやればちゃんと出来るでしょう?」
唇を離して、くすりと笑う桐生、メガネを外して、ポケットにしまう。
「あんた…っ、あたしが言ったからそれで…っ?」
「あんまり見えないんですけどね?やはりあると邪魔になりますね?」
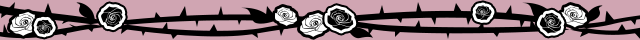
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える