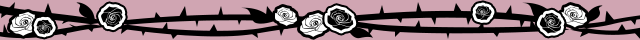
子供じゃない…上司に大人にされ溺愛されてます
第8章 本当に好きな人
涼くんのことは、決して嫌いになった訳じゃない。
ただ、涼くんは幼馴染みで、初恋の人で、家族みたいな人だから、
好きなのは変わらない。
恋してなかった訳じゃない。
だけど……、誠也さんは違う。
仕事で何かある度に、誠也さんの存在が、気が付いたら支えになっていた。
不安な時、辛い時、気が付いたら、いつもその存在を目で追って、
たった一言の会話だけで、頑張れた。
誠也さんに認められて、嬉しかった。
会社で少し会っただけで、一言会話しただけで、挨拶しただけで、
視線が合ったそれだけで、嬉しくて頑張れた。
もっと頑張れば、もっと関われる、仕事としてでも、それだけで、良かったのに。
……あの時、他の人に触れられて、怖いと思って、助けを呼んだ名前は、
誠也さんしか浮かばなかった。
誠也さんしか、呼ばなかった。
そんな自分に驚いた。
……あたしは誠也さんが、好きなんだ。
総務課の部長だからだとか、それは仕事として求めて、頼りにしてただけで、
それだけじゃなかった。
最初からそれだけの気持ちじゃなかったんだ。
そう、気が付いた瞬間、目頭が熱くなった。
あたしの気持ちに気付いて、待ち合わせ場所に、誠也さんを呼んだ涼くん。
来てくれた誠也さん。
……変わらない気持ちで、あたしを好きだと言ってくれる誠也さん。
その全てが、嬉しくて、信じられなくて、目の前にいる誠也さんを、
ただ見惚れるように見つめてしまう。
「愛莉、本当に俺でいいのかい?今更だけど俺は麻生に言われて、図々しく君を家にまで連れて来ちゃったけど、麻生のとこに帰るのなら、今のうち…」
誠也さんが言い終わらないうちに、精一杯背伸びして、その唇にキスをした。
ちゃんと届ききれずに、唇の下のほうにずれちゃったけど、
すぐに離れて、驚いたように目を見開く誠也さんを、じっと見つめて、
一生懸命笑って見せた。
「あたし…誠也さんが好き…っ、…大好きです…っ」
本人を目の前にして、そういったのは、考えてみれば初めてのことで。
信じられない、
そういうように、驚いたような顔をして、あたしを食い入るように見つめている誠也さん。
「……本当なのかい?……愛莉…っ、ああ、夢みたいだよ?」
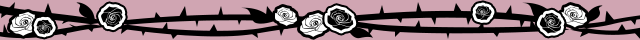
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える