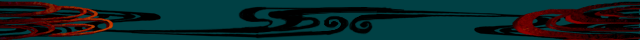
双龍の嫁
第1章 水龍
時が過ぎるのも忘れ、わたしは学び、楽しみ、愛し合いました。
まだお嫁入りしたばかりで娘気分が抜けないわたしを夫は可愛がってくれました。
眠る前に彼が話してくれる昔の人びとや世界の物語はとても面白いもので、わたしはつい時間を忘れてもっととせがんでしまいます。
「また昔の話が聞きたいのかい? そうだな……何百年前の事か忘れたが……いっときどこぞの国の勇者だという者たちが、ひっきりなしにここにやってきていてね。 私はただでさえこの風貌だろう? 口々に私を征伐すると言ってきた」
「まあ。 それじゃまるであなたは悪者扱い。それで、どうなりましたの?」
「一年ばかりここで昼寝をするんだよ。 彼らはこんな深いところまでは来れない。 そしたらそこらで水龍はとんだ臆病者なのだと噂が立つのだよね」
夫が穏やかな人なのは最初の印象の通りでしたが、一緒にいる間も一度も声を荒らげることなどありませんでした。
「それでは……そんな噂が立つのは仕方がないのかもしれませんけど」
彼はこんなに大きくて力強いというのに。
「それでもそうやってやり過ごしていれば、噂なんて消えてしまうのさ。 その者たちも歳を取り、やがて私の事を忘れてしまう。 流れる血で水が汚れ、同胞たちが苦しむ姿を見る方が嫌なんだよ」
どこからともなく散る泡は弾けながら揺らめき、遥か昔の記憶を辿るように、湖面への道しるべを作ります。
かと思うと、それらは陽の光を浴びた途端に、まるで子供たちがはしゃぎながらせわしなく笑い踊るかのごとく姿を変えて、最期は空へと還っていくのです。
臆病者の夫に呆れたかい? 彼がわたしの背中に回した腕を緩めて訊いてきます。 その眼の上にある眉のように見える骨が僅かに下がり、どこか不安げな表情に見えました。
「いいえ。 ちっとも」
おだやかに凪ぐ水が、夜更けまで語り続けるわたしたちを天蓋のベッドのように包み、そのうちにわたしの方が先に寝入ってしまいます。
そして眠りに落ちても湖の森で語りかけてくる夫のその声は、いつまでも子守唄のようにわたしをくるんでくれるのでした。
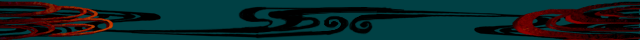
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える