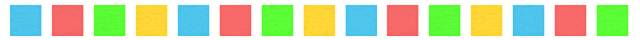
許容範囲内
第2章 誘う
おしぼりを手の上で転がして広げる。
「まさか八条さんが僕を誘うなんて」
「食べ終わったら泊まっていけ。終電も三十分後だ」
目を丸くする一川に、流石に強引だったかと熱燗を舐めて反省する。
このまま帰すのもどうかと思ったんだ。
だが、あのまま眠りにつくのも難しい話で。
一度頭を冷やして腹に何かを入れたほうが良いと。
店でなら、美容院と同じ温度で話ができる。
「こういう風に時間を気にせずに飲むのも久しぶりなんだ」
「別れたの最近なんだよね」
「二週間か?」
刺身を醤油にひたひたに漬ける一川の手つきを見つめて、マグロを舌に乗せる。
「だが、不思議なことに寂しいとは思わないんだ。十年以上連れ添っていたのにな」
「僕は二か月って言ったよね」
「多分そのうち耐え切れなくなるんだろうな」
独身は楽だとはいえど、一度家庭を経験し、その居心地の良さに救われていた者にとってはそう気軽なものではない。
毎日見送り、出迎えてくれる妻がいる。
それも愛し、愛されて。
「捨てられたっていうのは……」
「そこ聞くか」
ヒレ酒を店主から受け取り、香りを確かめる。
「抜擢されたんだ。海外の支社に。それで俺を置いて行った」
脳まで焼くような舌触りに眉を潜める。
味は確かだ。
この刺激が堪らない。
「でも、なんで」
「俺が行くなっていったんだ。結婚前に約束していたからな。美映……あいつが仕事を優先すれば縁を切ると。それにしても海外だぜ? 行くなら離れようって、あいつから言い出したんだ。約束を持ち出して」
不味くはならないものだな。
こんな話でも。
むしろ、過去を清算していくようで酒を楽しめる。
一川は、カチカチと箸を皿にぶつけている。
「どうした」
「考えられない。こんな良い男を……」
やけに真剣な眼差しで言うものだから、声を上げて笑ってしまった。
カウンターに突っ伏して。
「っははは……なんて目してるんだ」
「え、僕?」
戸惑って目を指先で揉む仕草まで笑えてしまう。
「周りの奴はみんな俺の味方をしてくれたけどな。結局離婚届にサインするのは最終的には俺の意思なんだよ。あそこでプライドを捨てて、あいつに縋りつけばよかった話だ」
深夜の酒は、人を脆くする。
笑った矢先に悲しみに暮れる。
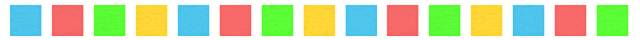
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える