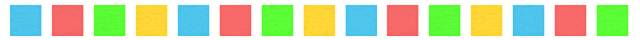
許容範囲内
第4章 疑う
「ご注文はお決まりでしょうか?」
涼しい声が場を冷やす。
頭と一緒に。
「えーっと、コークハイボール二つ。ハイボールひとつ、カルビとシロと牛タンと豚レバーと、あとカルビクッパ」
「それとオイキムチ」
「じゃ、それ二つ」
一川のオーダーに合わせる二階堂を一瞥して、八条は店員に会釈した。
「以上で」
「八条ちゃんは?」
「え……じゃ、この若鶏と三元豚で」
「畏まりました」
復唱して去って行った女性を二秒ほど見ていたが、三人は合わせたようにテーブルに腕を乗せた。
あまりに動作が揃ったので、緩く噴き出した。
二階堂は拳で唇をなでるように笑う。
いちいち格好がつくのだから、素晴らしい歳の重ね方をしている。
「なんで牛いかないの。食欲あるんだろ」
「なんとなくですよ」
入店時から感じるこの居心地の悪さは何なのだろう。
八条はお通しが来ても、手を付けようと思わなかった。
奇妙なものだ。
出会ったばかりの友人が、よく知ってきた同僚と楽しそうにしている。
この気分に名前があるとすれば、教えてもらいたい。
顎を手の甲で支えて、暗い照明を見上げる。
数秒まったく音のしない時間が流れた。
「なんていうかこう、何話せばいいのかわからんですね」
「俺には敬語、一川ちゃんにはタメってのが話しにくいんだろ」
「知ってていいますか、それ」
「それ言っちゃったら僕とか部外者ですよ」
「バツイチ同士は、二人だけどな」
少し拗ねたような物言いに何と返せばいいのかわからなくなる。
「笑いごとでもないんですけど」
「お待たせいたしました」
素晴らしいタイミングで店員が現れる。
並ばれていく料理に、普段は提供する側であるシェフ二人には毎回ながら手持無沙汰な感覚を覚えさせられる。
一川だけは無邪気に目を輝かせた。
グラスを手にした三人が、目を合わせる。
「お疲れ、乾杯」
音頭を取ったのは二階堂だった。
力強く小気味よい音が響く。
―かんぱーい!―
脳裏に七瀬との乾杯の音が過ぎった。
わいわいと暖かい空気と一緒に。
炭酸が喉に下っていく。
目の前には黄金がかった透明、視界の隅には黒いコークハイボール。
何かを飲むときの視界というのは日常の中でも不思議だ。
水面下とも違う。
「あーっ、甘いな」
「甘いね」
「二階堂先輩、コーク派じゃないでしょ」
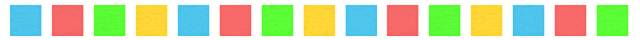
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える