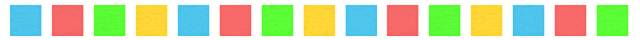
許容範囲内
第2章 誘う
「八条宏は渋いだろ」
テーブルに腕をついて散らばっているものを整理しながら呟く。
「じゃあ、なに?」
トコトコとついてくる一川は少年のようだ。
ウェットティッシュで軽くテーブルを拭き、椅子を引いて腰かける。
「勲だ」
「い、さむ? しっぶ」
「一川カイザー」
「なんで」
キラキラネームに苦笑する。
「蓮真。花の蓮に、まこと」
「はすま? キラキラ……」
「じゃないよ」
笑いながら足を組んで机に腕をもたれかける。
一川は所在無く、服の裾を摘まんで立っている。
用は済んだわけで、沈黙は居づらさを生む。
なんとなく、兄弟のように他人であっても気にはならない存在ではあるが。
「僕、そろそろ……」
「駅まで送る」
「え、でも」
コートを羽織る八条はスタスタと玄関に向かう。
靴下の毛の感触が気になるこの感覚。
なんだろうな。
八条は冷たいドアに額を当てて、ため息を吐いた。
「早く来い、一川くん」
大きめの声で呼ぶと、すぐに足音が聞こえた。
「車、ですか」
「そんな顔されるなら歩くが?」
職場が同じわけでもなく、三十を過ぎた男が二人で素面で歩くのもなかなかないもので。
コツコツと革靴を鳴らし、暖かい光の列をぼんやりと眺める。
今の時間なら居酒屋も多少は空いてるか。
「八条さんの店ってどんな感じ?」
「値段はまあまあか。芸人とかもたまに来る」
「プライベートでとか」
「昼のグルメ番組とかで取材が来たりもあったな。その時のレポーターとは結構仲良くなった縁があったり。基本は厨房だからそこまで前には出ないから、客のことまではよくわかんないが」
気づけば入るつもりで店を探しながら話している。
一川は未だ少し申し訳なさげに肩を落として歩く。
「じゃあサインとか飾ってるんだ」
「そういうの飾る店じゃないんだ。三人くらいはガラスのショーケースか何かに入れて……お。ここは空いてるな」
「え?」
立ち止まった八条が見つめていたのは、前から気になっていた海鮮居酒屋だった。
店頭のお勧めメニューには鯛めし。
「一川君、鯛は好きか」
「は、あ。好きだけど」
既に暖簾をくぐって細い入り口を進んでいく八条に唖然とするも、路地を見渡して帰るわけにもいかずに走った。
引き戸を開けて、オレンジの光が柔らかく照らす店内に入る。
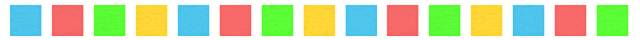
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える