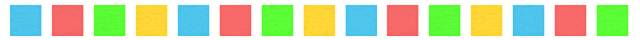
許容範囲内
第3章 連れ出す
「コーヒー、飲み終わったらまたね」
そう言って男の性器をしまい、ベルトをきつく締めてやる。
ハッとしたように目を見開いて、慌ただしく出ていく姿はなんとも間抜けだ。
攻めるときは野獣のくせに。
一川は洗面所で丁寧に口をゆすぐと、窓際の席にのんびりと戻った。
標的になった男が働く様を楽しく眺めて。
そうだ。
こちらから値定めるようになったのは、二十歳を過ぎてから。
年下の男子と付き合ってからだ。
一川はコーヒーを少しずつ口に含む。
デート中に手洗いで知らない男と性器を擦り合い、泊まると言ってコンビニに買い出しに出掛けて店員とセックスをした。
どうやらそうした類いの男からは好まれる容姿に恵まれたようで、相手に困ることはなかった。
一川自身性欲が強く、毎日自慰に頼っていた十代までが嘘のように他人と慰めあった。
コーヒーの湯気が消える。
だけど、それもあの人で最後。
そのはずだった……
冷めていく黒い液体が、先程までの快楽も醒ましていく。
左手の薬指にもう痕はない。
唯一、生涯を誓った人はもういない。
いなくなった。
無責任な約束と、消えることのない思い出を刻み付けていなくなった。
銀色のリングは引き出しの一番上に。
写真はアルバムに。
全て残したまま。
一川の視界が狭くなっていく。
睫毛が世界を閉じるように。
ああ、そうだ。
あの頃は、別れた頃は毎日こうだった。
世界が狭くて遠かった。
愛する人と別れることが、こんなにも空虚だなんてと世を恨んだ。
あの人を恨むことはできなかったから。
ふと顔を上げると、ルフナの方に人の列が見えた。
まだ開店時刻には半刻も早いのに。
八条の店の人気は確かのようだ。
九出と五木の姿を思い出して、心が翳る。
不信感を丸出しにしてくるほど、八条は大事にされている。
愛されている。
スゴいことだ。
だから、手を出したくない。
まだ。
優しくて、周りを変えられる人だから。
テーブルに指先で文字を書く。
八条勲。
二十四画の三文字を。
それからコーヒーを飲み干して、ウェイターにアイコンタクトを送ってから手洗いの木の扉へと闊歩した。
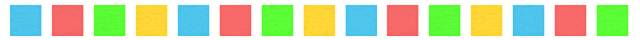
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える