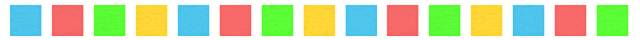
許容範囲内
第3章 連れ出す
「八条さん、チーフリーダーがお呼びです」
洗い場のヘルプで皿を片付けて棚の前で屈んでいるときに、三池が声を掛けて来た。
熱いままの皿を急いで置いて、すぐにレストランに面した厨房の出口へと向かう。
「おっと」
危うくぶつかりかけたのは私服姿の二階堂だった。
「八条ちゃーん、店内は走っちゃ駄目だろ?」
「えっ、何やってんすか」
今日はシフトに入っていないはずだ。
メインディッシュ担当で、海外修行を経た彼は厨房一厳しいと言われる二階堂鈴夜。
スカイブルーの襟がピンと立ったシャツに臙脂のチョッキを組み合わせ、ぴっちりとした白いパンツを履きこなしている。
靴はイギリス製らしい橙の綺麗なフォルム。
明るく染まった前髪だけが茶色で、あとは黒髪というスタイルも独特だ。
「たまにはオレの手じゃない朝飯が食いたくて。でもオーナーいないのな、今日」
「ええ」
五十を過ぎたとは思えないエネルギッシュな人だ。
目線だけでチーフを探すと、二階堂の後ろに立っていた。
「来てますよ。さっき話してた方」
口パクでそう伝えて仕事に戻っていく。
去り際に走らせた視線の先に、一川が座っていた。
物憂げに頬杖をついて、窓際の席で陽光を浴びている。
先に注文したらしいカフェオレのストローをいじり、店内を眺めている。
「厨房放っておいてどうしたんだ」
「あ、その……今日俺の客が来てまして」
「奥さん?」
「残念ながら離婚してるんですよね」
「知ってる」
「ですよね……」
大きな手を擦り合わせて陽気に笑う。
五木も九出も凡人に見えるほどこの厨房には変人が揃っている。
ばしばしと背中を叩かれて、ホールに連れ出される。
「で、どの客?」
「一緒に挨拶する気ですか? 作ってないのに」
「いつもはオレが作ってるわけだし」
一川がふと顔を上げて、こちらに気づいた。
ふにゃっと笑顔を見せて、控えめに胸元で手を振る。
朝の情けない姿が夢のような爽やかさが、この店に似合っている。
「さっきぶりです。あ、僕は一川と申します」
すぐに二階堂に会釈する。
「おう。物腰ご丁寧にどうも。八条ちゃんの先輩の二階堂だ」
「先輩?」
「ああ、人生の」
先輩と呼ぶのは俺だけじゃない。
オーナー以外は統一されている。
にしても三十過ぎて「ちゃん」付けはやめて欲しいのだが。
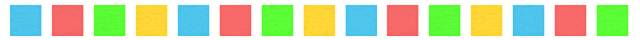
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える