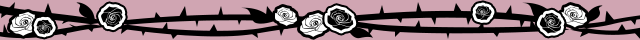
緋色の罠
第3章 緋の誘惑〜罠
"いただいたおいしい紅茶がある"と言ったのは嘘ではない。知人からもらったフランスブランドの高級茶葉があった。夫はコーヒー党なので紅茶を飲むのはわたしだけ。
木島さんをリビングに案内してソファに座らせた。
そのソファで毎日わたしが淫靡な行為に耽っていることを思い、恥ずかしさで身体が熱くなる。
「あ、ええと、支度しますからどうぞ寛いでいてください」
「はい。ありがとうございます」
リビングルームに隣接しているキッチンで紅茶の支度を始める。お湯を沸かしてポットと茶葉を用意しながら、木島さんをさりげなく盗み見る。
目が合ってしまった。
慌てて目を伏せ、キッチンボードの扉を開けてティーカープを取り出す。
何となく場を繋ごうと思い、以前から気になっていたことを聞いてみる。
「木島さん、よく昼間お会いしますけど、失礼ですがお仕事は?」
「ああ、警備会社に勤めているんです。夜のシフトが多いもので」
「警備会社というと、ガードマンですか?」
「いいえ。施設常駐のガードマンじゃなくて、何かあったら駆けつける警備員。ほら、ア〇ソックとか〇〇警備保障とか。テレビCMで聞いたことありませんか」
「ああ!知ってます」
テレビはあまり見ないが、その名前は知っている。結婚前に勤めていた企業のビルの警備も、その警備会社だったように思う。
木島さんをリビングに案内してソファに座らせた。
そのソファで毎日わたしが淫靡な行為に耽っていることを思い、恥ずかしさで身体が熱くなる。
「あ、ええと、支度しますからどうぞ寛いでいてください」
「はい。ありがとうございます」
リビングルームに隣接しているキッチンで紅茶の支度を始める。お湯を沸かしてポットと茶葉を用意しながら、木島さんをさりげなく盗み見る。
目が合ってしまった。
慌てて目を伏せ、キッチンボードの扉を開けてティーカープを取り出す。
何となく場を繋ごうと思い、以前から気になっていたことを聞いてみる。
「木島さん、よく昼間お会いしますけど、失礼ですがお仕事は?」
「ああ、警備会社に勤めているんです。夜のシフトが多いもので」
「警備会社というと、ガードマンですか?」
「いいえ。施設常駐のガードマンじゃなくて、何かあったら駆けつける警備員。ほら、ア〇ソックとか〇〇警備保障とか。テレビCMで聞いたことありませんか」
「ああ!知ってます」
テレビはあまり見ないが、その名前は知っている。結婚前に勤めていた企業のビルの警備も、その警備会社だったように思う。
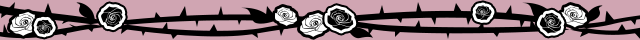
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える