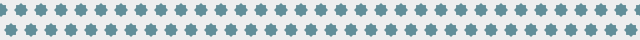
「先生、食べちゃっても良い?」
第2章 特別室
何か話す言葉が見つからず黙っている私に、曽根崎君はまたニコリと微笑む。
「あ、やめて欲しくなかった?」
「そ、そんなわけないでしょ!」
私は今の隙にと、乱れた下着やスカートとシャツを急いで整え、調子に乗っていそうな曾根崎君の事をまたきつく睨んだ。
(どうしよう。私……生徒と、何て事を……)
最後までしていないけど、もし誰かに知られたら二人共もうこの高校にはいられない。
私なんか教師の職を失う事になってしまう。
(……そんな事、考えただけでゾッとする)
嫌な想像をしたせいで、ブルっと体を震わせる。
そんな私とは真逆で、曽根崎君は能天気に微笑んでいる。
「俺と付き合ってくれたら最後までしてあげるよ?」
この言葉を聞いて「うん」と返事をするなら、私に教師の資格はない。
だからきっとこれからも何度迫られようが、私の答えはただ一つ。
「付き合うわけないでしょ!」
「あ、やっぱりー?」
厳しい口調で答えた後、私は内心焦っていた。
本当はこれからもし同じ様に迫られた時、今みたいに断れるかどうか自信がない。
それが何故なのか……私が理由を知る日はそんなに遠くない。
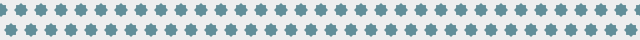
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える