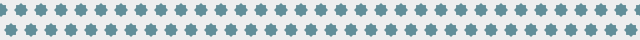
「先生、食べちゃっても良い?」
第2章 特別室
第一今キスした事も誰かに見られでもしていたら、二人の状況は最悪なものになる。
それなのに……何故キスなんてしたんだろう。
(曾根崎君……本当に危機感がなさ過ぎる……)
ギュッと握りしめられたままの両手。
そこから曽根崎君の暖かい体温が伝わってきてドキドキしながらも、私は俯きがちに答えた。
「ご、ごめんなさい。私、曾根崎君とは付き合えません。もしあなたが勉強を頑張るとしても、それは他の方法でやる気を出させれるように頑張ります……」
「ふーん、良いの? 俺のヤル気を出させる事なんて、すっごく簡単だよ? 」
「簡単って何が……」
不思議になって顔を上げた私が悪いのか、何か企んだ様に曽根崎君が口角を上げたかと思うと、また優しくキスをされる。
(油断した……)
相手は年下の学生だというのにそのまま唇をペロッと舐められると、一瞬教師と生徒の関係なんて忘れれてしまいそうになった。
そのまま耳元で囁いてくる甘い声にもくらっと眩暈がしてしまい、
「こうするだけ。ね? 簡単でしょ?」
「曾根崎君……だめよ……」
恥ずかしさもありぎゅっと目を瞑ると、続けて攻める様に曾根崎君の息が耳に掛かる。
「俺、キス好きなんだ。もし毎日こっそりしてくれたら、授業真面目に受けるよ? センセ」
(何言ってるの、この子……毎日こっそりキスなんて、絶対出来るわけない……)
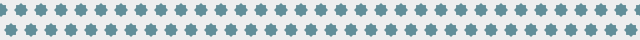
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える