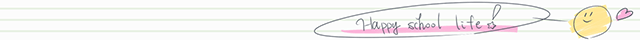
先生…お願い。早く治して・・・
第15章 検査
もう少し…もう少しの我慢…と、自分に言い聞かせ、
恥ずかしさと、くすぐったさを我慢した。
こんな状況でもつい、目を盗んでついつい先生を見てしまう。
画面を見つめる先生の目はとても真剣で、“星を見に行こう”と、私を誘った時の軽いノリは今の先生には微塵も感じられない。
それだけに、この部屋に2人きり…。
恥ずかしさと、この静けさが耐え難かった。
聞こえるのはピッ、ピッと時折聞こえる小さな電子音だけ。
ピピッピピッピピッーー
先生の手が止まった。
「少し腫れてるかな〜……」
っと、小さな声で独り言のように呟いた。
先生は画面に映る音のなる箇所の辺りを念入りに見ている。
……やっぱり私……悪い病気?
…先生…早くなんとか言って…、とはいえ先生の口から出る言葉も怖くて聞きたくない気もした。
「うん。」
小さく独り言のように呟いた先生は、温かいタオルを取り出すと、お腹に付いたゼリーを優しく拭き取った。
なんで何も言ってくれないの?
そんなに悪いの?
不安で頭はいっぱいだった。
「今度は軽く膝曲げて。」
先生は私の膝の下に手を添え膝を持ち上げた。
私は下半身を隠しているタオルがずれないようにぎゅっと握りしめた。
「ちょっとお腹触るよ。痛かったら言うんだよ。」
私はコクンと頷いた。
先生の綺麗で優しい大きな手が、さっき大きな音が出た辺りを探る。
「どお?痛くない?」
私はまたコクンと頷いた。
「じゃあ、ここは?」
体が小さくビクンと反応した。
『……大丈夫です…。』
先生は困ったな…という表情を浮かべながら、大きく溜め息をついた。
そしていつになく真剣な目で私の目を見ると
「綾ちゃん…。嘘はいけないよ。』
『…………。』
言葉が出なかった。
「いいかい"痛くない"って嘘を言っても、検査や治療をしなくて済むわけじゃないんだよ。我慢したからって、自然に治るわけじゃないんだよ。」
その言葉に目の前が真っ暗になった気がした
恥ずかしさと、くすぐったさを我慢した。
こんな状況でもつい、目を盗んでついつい先生を見てしまう。
画面を見つめる先生の目はとても真剣で、“星を見に行こう”と、私を誘った時の軽いノリは今の先生には微塵も感じられない。
それだけに、この部屋に2人きり…。
恥ずかしさと、この静けさが耐え難かった。
聞こえるのはピッ、ピッと時折聞こえる小さな電子音だけ。
ピピッピピッピピッーー
先生の手が止まった。
「少し腫れてるかな〜……」
っと、小さな声で独り言のように呟いた。
先生は画面に映る音のなる箇所の辺りを念入りに見ている。
……やっぱり私……悪い病気?
…先生…早くなんとか言って…、とはいえ先生の口から出る言葉も怖くて聞きたくない気もした。
「うん。」
小さく独り言のように呟いた先生は、温かいタオルを取り出すと、お腹に付いたゼリーを優しく拭き取った。
なんで何も言ってくれないの?
そんなに悪いの?
不安で頭はいっぱいだった。
「今度は軽く膝曲げて。」
先生は私の膝の下に手を添え膝を持ち上げた。
私は下半身を隠しているタオルがずれないようにぎゅっと握りしめた。
「ちょっとお腹触るよ。痛かったら言うんだよ。」
私はコクンと頷いた。
先生の綺麗で優しい大きな手が、さっき大きな音が出た辺りを探る。
「どお?痛くない?」
私はまたコクンと頷いた。
「じゃあ、ここは?」
体が小さくビクンと反応した。
『……大丈夫です…。』
先生は困ったな…という表情を浮かべながら、大きく溜め息をついた。
そしていつになく真剣な目で私の目を見ると
「綾ちゃん…。嘘はいけないよ。』
『…………。』
言葉が出なかった。
「いいかい"痛くない"って嘘を言っても、検査や治療をしなくて済むわけじゃないんだよ。我慢したからって、自然に治るわけじゃないんだよ。」
その言葉に目の前が真っ暗になった気がした
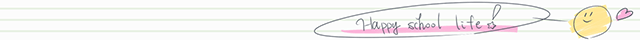
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える