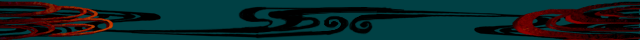
双龍の嫁
第2章 風龍
そんなわたしに構わず彼が声を掛けてきます。
彼が発する音は高くもなく低くもなく、そっと耳元でささやく時の声に似ています。
「ここでは私のしるしを分けよう。 こうやって、四六時中お前を抱いて空を飛ぶ訳にもいくまい。 その辺は水でも同じ理屈だったろう」
そして風龍はわたしのお腹をやさしく撫でました。
「あ……」
先ほど湖岸辺で感じたものと同じに、じんわりとする温かな感触でした。
「私の場合はここだ。 花嫁の神秘に護られ、その血潮とともに、常にここには風が凪いでいる。 我らの猛る雄根に貫かれようとな」
そう言って風龍は向かい合わせのままで私に自らをあてがいました。
彼の男性器は水龍のように長大なものではありませんでしたが、鎌首をもたげた赤い蛇に似ています。
それが圧しながら、おおきく拡げられたかと思うと侵入を始めました。
「んく……」
苦痛を押し殺した声が喉から出てしまい、彼はそれ以上進むのを止めました。
少しだけを埋めて、微かに膨らんだわたしの下腹を撫でていき、結合部の辺りでまた上へと、彼が自分のものを扱くように動いていきます。
「私の形がわかるな。 生娘だと面倒なんだが、温和な水龍に任せてよかった」
それはまるで内側に擦り付けられるのと似た感覚でした。
一抹の安堵感が、じりじりと熱を持ったあの刺激に変わろうとしています。
「こんなに溢れてるぞ。 もっと欲しいのか?」
初めての場ではしたない声を出さないよう、口に手を当てていたわたしは顔を熱くして目を逸らしました。
「よい。 私は放蕩な女が好きだ。 そうしたくなったらいつでも言え」
軽い笑みにも似た声とともに熱い何かが体内に迸り、驚いて体を仰け反らせましたが、風龍はがっしりとわたしを抱いて離しません。
喉を逸らしたまま、わたしは震えていました。
膣の奥底、そこを通って胎内になにかが入ってきます。
痛みを伴うものではありませんでしたが、まるでそこで空気の泡が弾けて集まり、疎らに散っていくような。
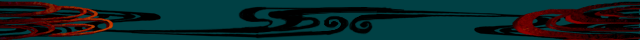
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える