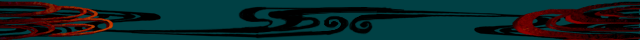
双龍の嫁
第2章 風龍
紫の色に沈みかける雲母に、対となった褐色の翼が遠ざかって行くのが見えます。
そんな風景を見詰めながら、夫がわたしに言葉を落としました。
「沙耶。 明後日からはまた水龍の所だな」
「……はい、でも」
────────最初のあの日以来、風龍はわたしを抱こうとしていませんでした。
身を寄せるとこのように腕を回してくれますし、わたしが寒さに耐えられる体になり、もうその必要がなくとも夜は暖かい胸に包んでくれます。
けれどそこに性的なものはありません。
「どうした?」
最初の日に、わたしが途中で彼を受け入れることを拒んでしまったからでしょうか。
……そういう対象には見れなくなってしまったのでしょうか。
こうやって触れ合っていると、あの狂おしいまでの官能の波を思い出し、ふたたび肌が粟立ってきます。
わたしの胎内に居る夫の一部。
ろうそくの炎のように揺らめくわたしの内のなにかが、そこをじりじりと焼き始めました。
「なんでも……ありません」
小さく息をつきそれだけ言うと、夫は力強く手のひらでわたしの肩を抱きつつみました。
「……っ」
わたしの体はどうしてしまったのでしょう?
とても夫には言えません。
こんなことで、声をあげそうになるだなんて。
夫の手はわたしを離しませんでした。
そうやってすっぽりと覆われた肩は痛いほどで、それなのにその先の指たちは、わたしの二の腕をやさしく撫でています。
薄い肌を指の腹がそっと這うたびに、わたしは震えました。
「まだ冷えるのか。 もう平気な体になったと思ったのだが。 膝に乗るか?」
夫はわたしを気づかって、暖めてくれているつもりなのでしょう。
わたしの膝の下に手を差し込むと、横抱きにして胡座をかいているその上に乗せてくれました。
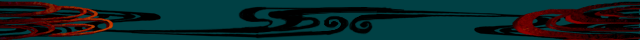
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える