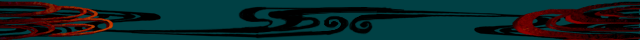
双龍の嫁
第2章 風龍
薄い衣服の生地を通して夫の胸や腕、腿が押し付けられ、顔が熱くなるのを感じます。
辺りがすっかり暗くなった岩場の洞には、蝋の灯りがいくらか点されているだけで、夫の胸元に細いうぶ毛が金色に透けていました。
初めてそれに気付いたわたしは妙な感慨を覚え、そっとそれに頬を擦り付けます。
唇の粘膜に当たるやわらかな感触に、思わずうっとりしていると、首元を支えていた腕の力がふっと抜けたのを感じました。
顔を上げると、困ったようにまなじりを下げて苦笑いしている夫と目が合いました。
「そう煽るな。 お前に無理はさせたくないのだ」
透き通る瞳の中に、翡翠に染まったわたしの顔が映っています。
その下でうごめく唇の形は直線的で、否が応でも男性を感じるのに、桃よりも薄い蘭の花びらと見紛うほどに繊細な色をしています。
それに誘われて弾力のある唇に指を伸ばすわたしを、龍はじっと見つめていました。
白い肌に筋肉質な体。
一見無機質な瞳は森緑の安寧をたたえ、気ままに揺れるものを信条としつつもその心はわたしを捕え。
彼は相反する要素をいくつも持っています。
わたしの指先がしっとりとした唇の内側に触れた時、夫の堪えるようなため息がその隙間から漏れました。
「沙耶、どうしたい」
彼はたしか、言いました。
「あなたが…欲しいのです────…」
……そうしたくなったらいつでも言えと。
握られた指に気を取られる前に、彼が屈みこみわたしに顔を近付けました。
そういえば、夫がなにかを口にするのをわたしは初めて見たような気がします。
その対象がわたしなのかと、こんな時だというのにほんの少しだけ、可笑しく感じました。
「……──────」
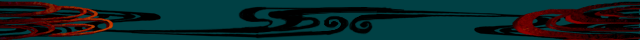
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える