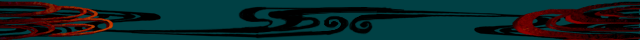
双龍の嫁
第2章 風龍
「ぁん、ッん…そこ、は…」
あの最初の日のような、奥の奥が潰されるような感覚。
それがなにかは分かりませんが、未知のものに対してわたしは恐れていました。
ただあの時と違うのは、浮いた腰もそのままに、まるで欲しがっているかのようにはしたなく脚を開いて夫を迎え入れていることです。
愛する者との交わりは、こんなにも体を溶かされるものなのでしょうか。
そんな自分に気付いて、戸惑いました。
「アッ…ぁあッ、ぁあ…ぃやあ…」
わたしの性器の上の方、そこの敏感過ぎる部分に、夫の恥骨がこすりつけられています。
そうしつつも彼はわたしの両腰に手を添え、結合を愉しむかのように腟の壁を探り続けます。
「お前の陰核が硬くしこってくるほどに……奥から柔らかくほどけて私を包んでくる。 以前とは違う反応だな?」
夫が陰核と呼ぶ、それの感覚が段々と鋭く耐え難いものになってきます。
「ほら…もっと可愛がってやるぞ」
そんな風に語りかけながら、急いて腰を揺らそうとしてしまうわたしに反し、夫は大きく動きません。
「アッあっ…はぅ…ァあぁッ…んぁァっ……」
下から上へと、肉の粒をやんわり撫であげて、その際に挿入が胎内の入口のしこりのようなものをぐっと押します。
「すっかり皮が剥かれて、まるで紅い真珠のようだな。 狭い蜜壷が絡んで……こんなものは、何百年振りの快楽か」
わたしのそこを凝視しながら、彼は焦らすかのように緩慢な動きを続けています。
ぎりぎりの波打ち際で与え続けられる快感は容量を増し、わたしの愛液が自身の臀部や腿を滴りました。
「ああ……子宮が開きかけている。 私を内から求めている、胎内のしるしのせいだろう」
窮屈そうに首をもたげるかのように収まっていた尖頭が、わたしの内部でびんっと真っ直ぐに反り返ったのが分かりました。
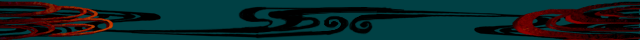
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える