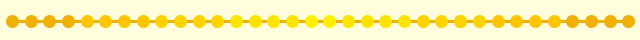
飼い猫 🐈⬛🐾
第40章 段取り
「あ… 香緒さん? 紫優です。
すみません… 詩史が 寝ちゃって…
このまま 泊まらせて良いですか?」
電話の向こうの 香緒さんは
『やっぱり…』と苦笑い。
あっさり お泊りの許可を取って 電話を切ると
じっとりと睨む 母親の視線に 気がついた。
「…何?」
「…詩史ちゃんに まだ言ってないんでしょ…!」
母親の言いたい事を 即座に 理解した俺は
気を重くする。
「… そうだね。」
「早く 言ってあげなさいよ?
詩史ちゃんだって 急に紫優と離れる事になったら 辛いでしょ?
心積もり させてあげないと 可哀想よ?」
母親の言葉に 視線を落とす。
詩史と 離れる…
今の俺達には 身を引き裂かれる様な
苦しい事だ。
きっと 詩史にも 苦しい思いをさせてしまう…
「…連れて行きたいな…」
「無理でしょ! って言うか 詩史ちゃんにだって 進路があるんだから…
これ以上 紫優の勝手な都合に 巻き込んじゃ
ダメ!」
母親に きっぱりと言い切られて
そうだよね… と納得する。
詩史は
お気に入りのぬいぐるみや ペットじゃないんだ。
そんな 簡単に 俺の都合で 持ち出せない。
部屋に戻って ベッドに腰掛けて
何も知らずに眠る詩史の 頭を撫でる。
詩史と 離れなきゃいけない なんて…
今は 考えたくない…
伝えなきゃいけないと わかっていても…
自分だって 納得出来ていない事を
詩史に 伝えられない…!
ぎし…っと 軋む音を聞きながら
ベッドに上って
詩史に覆い被さって キスをする。
「…やっと 振り向かせたのに… 詩史…!」
唇を 何度も啄んで 柔らかな唇を 堪能する。
舌を出して 舐めあげると 唇が濡れて…
ゾクッ と 身震いする。
ああ… ヤバい… 詩史を食べたい… !
頬を撫でて 首筋を伝って…
掛け布団をずらすと
詩史の綺麗な鎖骨が 現れた。
鎖骨にキスを落とすと
詩史の温もりに 目眩を覚える。
もっと 欲しくなるに 決まってるのに…
肩を撫でて 腕を撫でて… 布団をズラしていくと 綺麗な双丘が 顔を出した。
双丘の谷間に 顔を埋めて 頬擦りする。
温かい… 軟らかい…!
布団を 捲り上げて 詩史の 太ももを撫でる。
すみません… 詩史が 寝ちゃって…
このまま 泊まらせて良いですか?」
電話の向こうの 香緒さんは
『やっぱり…』と苦笑い。
あっさり お泊りの許可を取って 電話を切ると
じっとりと睨む 母親の視線に 気がついた。
「…何?」
「…詩史ちゃんに まだ言ってないんでしょ…!」
母親の言いたい事を 即座に 理解した俺は
気を重くする。
「… そうだね。」
「早く 言ってあげなさいよ?
詩史ちゃんだって 急に紫優と離れる事になったら 辛いでしょ?
心積もり させてあげないと 可哀想よ?」
母親の言葉に 視線を落とす。
詩史と 離れる…
今の俺達には 身を引き裂かれる様な
苦しい事だ。
きっと 詩史にも 苦しい思いをさせてしまう…
「…連れて行きたいな…」
「無理でしょ! って言うか 詩史ちゃんにだって 進路があるんだから…
これ以上 紫優の勝手な都合に 巻き込んじゃ
ダメ!」
母親に きっぱりと言い切られて
そうだよね… と納得する。
詩史は
お気に入りのぬいぐるみや ペットじゃないんだ。
そんな 簡単に 俺の都合で 持ち出せない。
部屋に戻って ベッドに腰掛けて
何も知らずに眠る詩史の 頭を撫でる。
詩史と 離れなきゃいけない なんて…
今は 考えたくない…
伝えなきゃいけないと わかっていても…
自分だって 納得出来ていない事を
詩史に 伝えられない…!
ぎし…っと 軋む音を聞きながら
ベッドに上って
詩史に覆い被さって キスをする。
「…やっと 振り向かせたのに… 詩史…!」
唇を 何度も啄んで 柔らかな唇を 堪能する。
舌を出して 舐めあげると 唇が濡れて…
ゾクッ と 身震いする。
ああ… ヤバい… 詩史を食べたい… !
頬を撫でて 首筋を伝って…
掛け布団をずらすと
詩史の綺麗な鎖骨が 現れた。
鎖骨にキスを落とすと
詩史の温もりに 目眩を覚える。
もっと 欲しくなるに 決まってるのに…
肩を撫でて 腕を撫でて… 布団をズラしていくと 綺麗な双丘が 顔を出した。
双丘の谷間に 顔を埋めて 頬擦りする。
温かい… 軟らかい…!
布団を 捲り上げて 詩史の 太ももを撫でる。
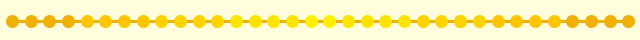
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える