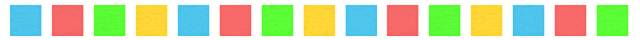
許容範囲内
第2章 誘う
まだ成人したばかりの二十一歳の彼女は厨房の最年少で可愛がられている。
外見は一般的だが、手入れの程が感じられる明るくしっとりとしたブラウンヘアの編み込み、清潔感を保った化粧具合が好評だ。
「届いてないのか」
ちらりと裏口を見遣る。
「それがー、今日早番の五木さんも業者見てないって仰ってるんですよ」
「今夜のディナー分は?」
「う……三十は仕込み済みで確保して」
「足りないな」
「はい……すぐ連絡します」
か細い声でそう呟くと、彼女は連絡ボードの脇に備え付けられた固定電話に歩いていった。
こういうのは朝のうちに解決しないと、店の信用問題に発展しかねない。
ベーコン用の塊肉は値上げしてから業者を変えたが、それ以降たまにこうしたズレが起きているらしい。
オーナーにまた相談しないと。
八条は前菜のストックから心配なものを脳内リストアップして、野菜を両手に抱えながら厨房に戻った。
ゴロゴロとザルに野菜を移し、冷水を勢いよく注いで洗う。
水音を聞きながら、今朝のことを思い出す。
朝日を浴び、何度アラームを止めても起きない一川を揺する。
「今何時だと言うの」
「六時だな。俺はあと十分で出勤するんだ。早く顔洗って支度してくれ」
「……八条さんの朝食楽しみにしてた」
「サンドイッチ作ってある」
「わあ、流石」
欠伸混じりに嬉しそうに笑い、洗面所に向かう背中を見つめる。
華奢だな。
あんなにも自分の服が大きく見えるとは。
シーツを直し、枕も整える。
二人分の寝跡は奇妙に見えた。
温もりも二人分残っているようで。
今夜から、また一人になるのか。
「八条さん、服ありがとう」
「洗濯機に突っ込んでおいてくれ」
「既に」
「そうか」
玄関でサンドイッチの入った袋を手渡し、マンションの下までエレベーターに乗る。
仕事モードに切り替えねばと、栄養ドリンクを飲み干す。
「二日酔いは?」
「大丈夫だ。一川くんは?」
「全然」
どの程度の距離感で話せば良いものかわからなくなっている自分がいた。
オートロックの自動ドアをくぐり抜け、駐車場に足を向ける。
「ここなら駅から近い。一駅なら送らなくても良いだろう?」
「まあ、ね。いってらっしゃーい」
「あ、ああ」
わざわざ駐車場出口で待っていた一川に見送られて出てきた。
本当に、不思議な訪問者だった。
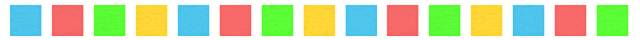
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える