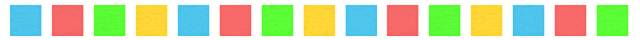
許容範囲内
第3章 連れ出す
何故か一川の向かいに相席することになり、二階堂がどっかりと腰かける元へ料理を運ぶ。
チーフの計らいで、配膳を任されたのだ。
モーニングセットの中で一番人気のCセットは、厚切りフランスパンのフレンチトースト、ローストナッツを散らした生ハムのサラダ、真鱈のソテーとニンジンポタージュ。
デザートには前日に仕入れるイチゴとチーズムースだ。
一川はそれほど食べる方ではないのでCにさせたが、二階堂は一番ボリュームのあるBセットだ。
フレンチトーストではなくハンバーガー、店で腸詰めしたソーセージがたっぷり入ったポテトグラタンが追加される。
テーブルに並んだ料理を見て、一川は嬉しそうに顔を緩ませた。
「どれが、八条さんの作ったものですか?」
フォークを手にして、楽しそうに。
「真鱈のソテーとグラタンだ」
「八条ちゃんの魚料理はやばいよね」
「褒めてます?」
談笑していたいが、まだ朝のピークが終わっていない。
「じゃあゆっくりしていってくれ」
「二階堂さんに八条さんのお話を聞いておきます」
「くははっ、とっておきの話しとくよ」
「やめてくださいよ、本当」
厭な笑いに見送られ、厨房に戻る。
それにしても美味しそうに食べる男だよ。
二階堂も楽しいだろうな。
話してみたら嫌う人はいないだろう。
「おかえり、八条さん」
「五木さん、また心配してたんですか」
フライパンを片手に苦い顔をしている五木に脱力する。
オーダーが溜まっているので相手にする暇も無くすぐに調理に取り掛かる。
九出はランチに向けての仕込みと常に入る注文とに挟まって苦闘する時間なので、からかう余裕もなさそうだ。
十時を回れば落ち着くので、それまでは水分補給をしつつ乗り切るのみだ。
汗が額に滲みつつある熱気の中、淡々と業務をこなす。
だが、油を敷いた鉄板に真鱈を置く数秒に間に思い出すのは一川の笑顔だった。
―どれが、八条さんの作ったものですか?―
あんなに無邪気な目で。
おかしいな。
離婚してまだひと月も経たないというのに。
美映がどんな風に食べていたのか思い出せない。
手を合わせて、目を瞑り箸に手を伸ばしてからが、浮かばない。
毎日見ていたというのに。
皿を引き寄せる左手の指を見下ろす。
指輪の痕。
流石にもう目立ちはしないが。
また填めることはあるだろうか。
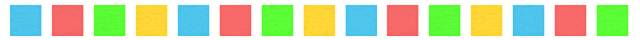
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える