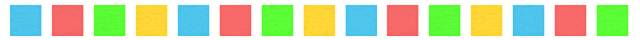
許容範囲内
第1章 愚痴る
メインは楕円形の皿に並べる。
米は、買っておいたんだった。
バターで軽く炒めて盛り付ける。
「一川君、そろそろ来ないか?」
「良い匂い」
振り向くと、冷蔵庫の陰からぴょこりと姿を現した彼に肩が跳ねる。
「い、いつから」
「メンチカツ盛り付けたあたりから」
「配膳くらいやってほしいが」
「酒は入れたよ」
気が早い。
ビールの泡も抜けかけているじゃないか。
「いただきます」
「いただきます。旨そう」
随分と簡単な料理にしてしまったが、それでも久しぶりの凝った手料理なのか一川はひとつひとつ丁寧に感想を述べて食べた。
幸せそうに。
気になっていたことだが、この男には離婚したことへの後悔や蟠りが感じられない。
清々しいのだ。
俺とは違って。
「八条さん、流石プロ。タルタルソースとか僕大好きなんで。これはにんにく加減が最高」
「そうか。ところで一川君」
「あ、乾杯」
「……乾杯。そうではなくてな」
今更ながら中身の減ったグラスを軽くぶつける。
妙にそういうところは拘るのか。
「君は何故離婚したんだ」
「何故、というと」
「美容室で言っていたが、学生時代からの付き合いだったんだろう?」
ビールを勢いよく飲み干して、一川は口を手の甲で拭った。
「まあ、僕のせいというか」
「浮気か」
「八条さん意外とぐさぐさ」
「恥じることでもないだろ」
胸に手を当てて傷ついたふりをする一川に冷たい目線を突き刺す。
「……八条さんも?」
「俺は捨てられただけだ」
「その正直さ、凄い」
勝手に感心する一川を横目に、この部屋に色濃く残った家庭生活を振り返る。
棚に並んだ写真。
彼女が選んできたテレビ台。
窓の装飾テープ。
時計にぶら下げたブリザードフラワー。
センスの良し悪しは知らないが、独自の世界を持った女性だった。
「まだ、慣れない?」
「ああ。勿論だ」
「僕は二ヶ月かかった。なにせ食事から変わるんだから、意識しないわけにはいかない」
「そういうものか」
食事。
妻として作らせてくれと何度も挑戦されたが、その度に完成したものを差し出して謝られる。
不器用な女だった。
それでも、そこが好きだったんだ。
「……八条さん?」
「こうして誰かとここで食べるのは久しぶりで、思い出すものが多いんだ」
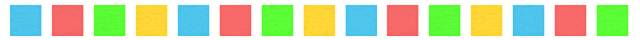
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える