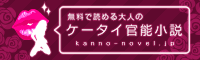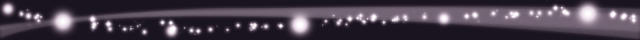
Kalraの怪談
第46章 四十六夜目:呼ぶ子
☆☆☆
「よく来なさった」
私が民宿の主の名を出し、紹介されたことを告げると、齢70も過ぎているだろうT先生は満面の笑みで迎えてくれた。学校の先生をしていただけあって、人と話すのは好きな様子だった。
案内された応接間には、土器や古銭、古道具、古今の書物などが所狭しと並んでいた。一人暮らしであるというT先生がお茶を用意してくれている間、私は部屋を見て回った。書棚には東北の民俗学や西洋の呪術についての本など様々な書物があった。一部にはT先生やT先生の父か祖父が著したと思われる本もある。
『A県の民話集』
『山奥夜咄』
『中世のS村民俗考』
などなど。その中の一冊、T先生の名が記された本に興味を惹かれた。
『【呼ぶ子】伝承考察』
パラパラとめくってみると今から20年くらい前にT先生自身が自費出版した書物のようだ。T先生自身の自筆のサインが表紙の裏に記されているところを見ると、贈呈用として準備したものの余りのようだった。
まえがきを読む。
ーーーーーーーーーー
A県S村字Oには昔から『呼ぶ子』という伝承がある。これは周辺の村には見られない、この地域独特のものである。私は7〜8歳時に祖父から『呼ぶ子』の話をよく聞き及んでいた。村の婆さんからも同様の話を何度か聞いたことがあるので、この話はS村ではよくよく浸透していたようである。
(中略)
語り手によって多少の違いがあるが、呼ぶ子の伝承は以下の通りである。
昔からS村近くの人が寄り付かないあたりに『呼ぶ子沢』という場所がある。そこは、比較的流れの早いS川の途中であるにもかかわらず、地形の関係で流れが弱く、透明で深い淵となっていた。
言い伝えではS川で溺れて死んだものの魂は、この淵に「溜まる」と言われている。
なので、呼ぶ子沢では、
人魂が飛び交うだとか、
夜中に泳ぐ赤ら顔の子どもがいるだとか、
マタギが森を歩いていると、バシャバシャと水音がするが、沢を見ても何もいないとか、
そういった話がたくさん聞かれる。
中でも恐ろしいのが、呼ぶ子沢で泳いだ子どもは、沢に溜まった魂たちに「引っ張られる」というのだ。泳ぎが上手な子であっても何かに足を引かれ、深みにはまって死んでしまう。
そして、呼ぶ子沢で子どもが死ぬと、その子は「呼ぶ子」になる。
ーーーーーーーーーー
「よく来なさった」
私が民宿の主の名を出し、紹介されたことを告げると、齢70も過ぎているだろうT先生は満面の笑みで迎えてくれた。学校の先生をしていただけあって、人と話すのは好きな様子だった。
案内された応接間には、土器や古銭、古道具、古今の書物などが所狭しと並んでいた。一人暮らしであるというT先生がお茶を用意してくれている間、私は部屋を見て回った。書棚には東北の民俗学や西洋の呪術についての本など様々な書物があった。一部にはT先生やT先生の父か祖父が著したと思われる本もある。
『A県の民話集』
『山奥夜咄』
『中世のS村民俗考』
などなど。その中の一冊、T先生の名が記された本に興味を惹かれた。
『【呼ぶ子】伝承考察』
パラパラとめくってみると今から20年くらい前にT先生自身が自費出版した書物のようだ。T先生自身の自筆のサインが表紙の裏に記されているところを見ると、贈呈用として準備したものの余りのようだった。
まえがきを読む。
ーーーーーーーーーー
A県S村字Oには昔から『呼ぶ子』という伝承がある。これは周辺の村には見られない、この地域独特のものである。私は7〜8歳時に祖父から『呼ぶ子』の話をよく聞き及んでいた。村の婆さんからも同様の話を何度か聞いたことがあるので、この話はS村ではよくよく浸透していたようである。
(中略)
語り手によって多少の違いがあるが、呼ぶ子の伝承は以下の通りである。
昔からS村近くの人が寄り付かないあたりに『呼ぶ子沢』という場所がある。そこは、比較的流れの早いS川の途中であるにもかかわらず、地形の関係で流れが弱く、透明で深い淵となっていた。
言い伝えではS川で溺れて死んだものの魂は、この淵に「溜まる」と言われている。
なので、呼ぶ子沢では、
人魂が飛び交うだとか、
夜中に泳ぐ赤ら顔の子どもがいるだとか、
マタギが森を歩いていると、バシャバシャと水音がするが、沢を見ても何もいないとか、
そういった話がたくさん聞かれる。
中でも恐ろしいのが、呼ぶ子沢で泳いだ子どもは、沢に溜まった魂たちに「引っ張られる」というのだ。泳ぎが上手な子であっても何かに足を引かれ、深みにはまって死んでしまう。
そして、呼ぶ子沢で子どもが死ぬと、その子は「呼ぶ子」になる。
ーーーーーーーーーー
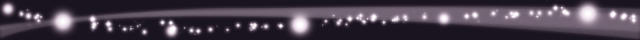
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える