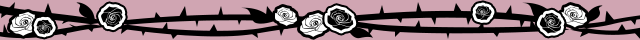
Lの劣情
第1章 2024年6月吉日…
5
わたしはいつもよりも心地よく酔っていた…
それは大好きな、大好きで憧れでもあり尊敬をしていた先輩との16年振りの羨望の再会の心の昂ぶりのせいでもあり、また、この春先に色々とした出来事があったせいでの心が落ち込んでいたという反動でもある…
とも、いえたのだと思われた。
「ふぅ、少し酔っちゃいましたぁ」
「え、みっき大丈夫なの?」
「あ、はい、全然大丈夫ですよぉ…」
そうそういう意味の吐き気とかを催す酔いではない…
まるであの頃の…
青春時代の…
楽しかった大学バスケ時代に戻った、いや、還ったかの様な昂ぶりの楽しさからの酔いといえたのだ。
今、思い返せばわたしのバスケ時代のピークは大学1、2年の時であり、その時期に一緒に、いや、このアイ先輩はわたしが13歳の時からのチームメイトであるから否が応でも気持ち、テンションは昂ぶり、昔に還ってしまうのである。
「もうすっごく楽しいですぅ」
「うん、私も楽しいわ…
だってずうっとみっきに会いたかったから…」
今、時間は午後11時過ぎ…
そしてアイ先輩はもう一緒に泊まる事にして、わたし達は二軒目でこのホテルのバーで飲んでいた。
そのせいもあり、わたしは更に心に余裕ができていたのだ…
だって万が一にはホテルの部屋に戻ればいいのだから。
それにお酒に強いアイ先輩か傍にいるから…
わたし達はバーのカウンターで二人並んで飲んでいた…
さすがに週末のホテルのバーであるから、周りは…
「カップルばっかりですねえ」
女二人はわたし達だけであった。
「ええそうね、でも私はみっきと二人だから嬉しいわ…
本当にずうっと会いたかったのよ…」
そして…
「ずうっとみっきを心配していたのよ…」
そう囁き、わたしのカウンター下の膝に置いていた手を重ねてくる。
「あ…」
その手の感触に少しドキンとしてしまう。
「でもね、風の噂で高校の監督で活躍してるって…
そしたら今度はいきなりあの○○大学のアシスタントコーチって聞いたから…」
「あ、はい、ま、それは色々あって…」
「なんかいきなり急に近づけたから嬉しかったわ」
そしてアイ先輩はそう囁きながら、更にギュッと手を握ってきた。
わたしは急にドキドキと昂ぶりを感じてしまう…
だってその手が熱くなっていたから。
わたしはいつもよりも心地よく酔っていた…
それは大好きな、大好きで憧れでもあり尊敬をしていた先輩との16年振りの羨望の再会の心の昂ぶりのせいでもあり、また、この春先に色々とした出来事があったせいでの心が落ち込んでいたという反動でもある…
とも、いえたのだと思われた。
「ふぅ、少し酔っちゃいましたぁ」
「え、みっき大丈夫なの?」
「あ、はい、全然大丈夫ですよぉ…」
そうそういう意味の吐き気とかを催す酔いではない…
まるであの頃の…
青春時代の…
楽しかった大学バスケ時代に戻った、いや、還ったかの様な昂ぶりの楽しさからの酔いといえたのだ。
今、思い返せばわたしのバスケ時代のピークは大学1、2年の時であり、その時期に一緒に、いや、このアイ先輩はわたしが13歳の時からのチームメイトであるから否が応でも気持ち、テンションは昂ぶり、昔に還ってしまうのである。
「もうすっごく楽しいですぅ」
「うん、私も楽しいわ…
だってずうっとみっきに会いたかったから…」
今、時間は午後11時過ぎ…
そしてアイ先輩はもう一緒に泊まる事にして、わたし達は二軒目でこのホテルのバーで飲んでいた。
そのせいもあり、わたしは更に心に余裕ができていたのだ…
だって万が一にはホテルの部屋に戻ればいいのだから。
それにお酒に強いアイ先輩か傍にいるから…
わたし達はバーのカウンターで二人並んで飲んでいた…
さすがに週末のホテルのバーであるから、周りは…
「カップルばっかりですねえ」
女二人はわたし達だけであった。
「ええそうね、でも私はみっきと二人だから嬉しいわ…
本当にずうっと会いたかったのよ…」
そして…
「ずうっとみっきを心配していたのよ…」
そう囁き、わたしのカウンター下の膝に置いていた手を重ねてくる。
「あ…」
その手の感触に少しドキンとしてしまう。
「でもね、風の噂で高校の監督で活躍してるって…
そしたら今度はいきなりあの○○大学のアシスタントコーチって聞いたから…」
「あ、はい、ま、それは色々あって…」
「なんかいきなり急に近づけたから嬉しかったわ」
そしてアイ先輩はそう囁きながら、更にギュッと手を握ってきた。
わたしは急にドキドキと昂ぶりを感じてしまう…
だってその手が熱くなっていたから。
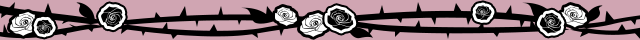
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える