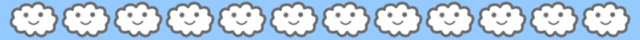
光の輪の中の天使~My Godness番外編~
第2章 流れた歳月
四年の歳月は想像以上に長かった。もう、この男に恨みも憎しみもない。たとえ、けして人には語れない経緯であったとしても、この男は理乃の父親、それだけは紛れもない事実なのだ。
「あなたも相変わらずなのね。そんな皮肉っぽい言い方しかできないの?」
実里ができるだけ感情をこめずに言うと、悠理は小さく笑った。
「済まない。どうも、あんたの前に出ると、素直になれないっていうか。これじゃ、まるでガキだな」
悠理の視線はずっと先、砂場で再び遊び始めた理乃に向けられていた。
この小さな公園にあるのは滑り台と砂場だけ。後は片隅に木のベンチ。その背後には、ひとかたまりの紫陽花がひそやかに咲いている。花の色は、まるでこの小さな町を母の腕(かいな)のように抱く穏やかな海と同じコバルトブルー。
「立ってるのは良くないだろう。座ろうか」
促され、実里は仕方なしに悠理の後から続いた。先に悠理が座ったので、隣に座るのをためらっていると、彼が立ち上がった。
「俺の隣に座るのがイヤなら、あんたが座ってくれ」
どうも心の中を見透かされているようだ。実里は赤くなった。それでも逡巡していると、少し強い口調で言われた。
「前にも早産しているんだぞ? 無理してまた、早くに生まれちまったら、どうするつもりだ。もし、そんなことにでもなったら、俺はせっかく気を利かしてくれた柊路に顔向けできなくなる。頼むから、座ってくれ」
その瞬間、実里は妙に思った。
どうして、悠理が理乃を生んだときのことを知っているのか―? 理乃は予定日より六週間も早く生まれた。妊娠34週の早産だったのだ。悠理の亡き妻早妃の墓参りに出かけた途中で産気づき、そのまま意識を失った実里を通りすがりの若い男が介抱し、親切にも病院まで運んでくれたと後で知った。
よもや、その実里を病院に運び、理乃の誕生までずっと付き添った男こそが悠理だとは知らない。悠理は病院を出る間際、ナースステーションに立ち寄り、自分が出産に付き添ったことは実里に話しても構わないが、赤ん坊の父親だと名乗ったことだけは内緒にしておいてほしいと頼んでいったのだ。
「あなたも相変わらずなのね。そんな皮肉っぽい言い方しかできないの?」
実里ができるだけ感情をこめずに言うと、悠理は小さく笑った。
「済まない。どうも、あんたの前に出ると、素直になれないっていうか。これじゃ、まるでガキだな」
悠理の視線はずっと先、砂場で再び遊び始めた理乃に向けられていた。
この小さな公園にあるのは滑り台と砂場だけ。後は片隅に木のベンチ。その背後には、ひとかたまりの紫陽花がひそやかに咲いている。花の色は、まるでこの小さな町を母の腕(かいな)のように抱く穏やかな海と同じコバルトブルー。
「立ってるのは良くないだろう。座ろうか」
促され、実里は仕方なしに悠理の後から続いた。先に悠理が座ったので、隣に座るのをためらっていると、彼が立ち上がった。
「俺の隣に座るのがイヤなら、あんたが座ってくれ」
どうも心の中を見透かされているようだ。実里は赤くなった。それでも逡巡していると、少し強い口調で言われた。
「前にも早産しているんだぞ? 無理してまた、早くに生まれちまったら、どうするつもりだ。もし、そんなことにでもなったら、俺はせっかく気を利かしてくれた柊路に顔向けできなくなる。頼むから、座ってくれ」
その瞬間、実里は妙に思った。
どうして、悠理が理乃を生んだときのことを知っているのか―? 理乃は予定日より六週間も早く生まれた。妊娠34週の早産だったのだ。悠理の亡き妻早妃の墓参りに出かけた途中で産気づき、そのまま意識を失った実里を通りすがりの若い男が介抱し、親切にも病院まで運んでくれたと後で知った。
よもや、その実里を病院に運び、理乃の誕生までずっと付き添った男こそが悠理だとは知らない。悠理は病院を出る間際、ナースステーションに立ち寄り、自分が出産に付き添ったことは実里に話しても構わないが、赤ん坊の父親だと名乗ったことだけは内緒にしておいてほしいと頼んでいったのだ。
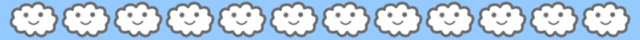
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える