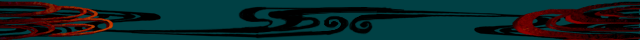
桜華楼物語
第5章 手鞠
この娘を手鞠と名付けたのは私だ。
若々しい身体と心は、まるで鞠のようにしなやかに弾み。
それをこの手の中で、慈しみ育み愛でる。
私の人生において、きっと最期の娘…。
吉原とはもう長年の付き合いとなる。
特にこの桜華楼は、とても気に入っている。
裏庭にある桜の古木は、その季節になれば満開の花を咲かせて。
散る花弁は風に乗ってはらはらと窓から舞い込み。
白い娘の身体に彩りを添えるのだ。
そんな桜華楼で、幼い手鞠は下働きをしていた。
貧しい農家の娘が口減らしで売られてきた。
吉原にはありふれた境遇の娘。
だが、暗い様子は無く。
小遣い程度の手当ての中から、少し貯めては家に送るような娘であった。
毎日食べられて働いて、それが店の役に立っているのなら幸せだと。
私は楼主にこの娘を預けてくれないかと申し出た。
そんな申し出は初めてでは無いから、また病いが出ましたな…と楼主は笑い承諾したのだった。
病いと言われれば、それも仕方がない。
自分の好みを注ぎ込んだ女を育てるのは…男としての私の性なのだろう。
私には息子は居るが娘は居ない。
もし血を分けた自分の娘に、この病いが出たら…。
考えるだけで冷や汗ものだ。
私が一代で築いた店は、もう息子に譲り気楽な隠居生活となり。
日々の老いと付き合いながら吉原に通う。
そんな時に手に入れたのが、手鞠なのだ。
手鞠はすぐに私に懐いた。
どうやら私に、故郷の祖父を重ねてるようだった。
膝の上に乗せてやったら無邪気に喜び。
そこは手鞠の指定席となったのだ。
私は彼女に、名前と共に日課を与えた。
少しずつ胸が膨らみ始め、しかしまだ無毛の恥丘のうちに出来る事を。
毎夜就寝前に、自分の乳首とさね豆を弄ぶようにと。
全裸になり姿見に映しながら、である。
最初はその行為に何の意味があるのか、きっと解らないであろうが。
日々を重ねていくうちに、徐々に変化していく。
処女の乳首とさね豆は、毎夜の刺激に感度と膨らみを増していき。
身体の奥で何とも言えない感覚が湧き上がり言葉にならない吐息が唇から漏れてくる。
姿見に映る己の姿を見て、動悸が跳ねて弄る手が止まらずに…。
どうしようもなく言い難い感覚が、脳天に突き抜けたら我慢せずに声をあげて。
そうやって逝き果てて眠りにつくのだ。
若々しい身体と心は、まるで鞠のようにしなやかに弾み。
それをこの手の中で、慈しみ育み愛でる。
私の人生において、きっと最期の娘…。
吉原とはもう長年の付き合いとなる。
特にこの桜華楼は、とても気に入っている。
裏庭にある桜の古木は、その季節になれば満開の花を咲かせて。
散る花弁は風に乗ってはらはらと窓から舞い込み。
白い娘の身体に彩りを添えるのだ。
そんな桜華楼で、幼い手鞠は下働きをしていた。
貧しい農家の娘が口減らしで売られてきた。
吉原にはありふれた境遇の娘。
だが、暗い様子は無く。
小遣い程度の手当ての中から、少し貯めては家に送るような娘であった。
毎日食べられて働いて、それが店の役に立っているのなら幸せだと。
私は楼主にこの娘を預けてくれないかと申し出た。
そんな申し出は初めてでは無いから、また病いが出ましたな…と楼主は笑い承諾したのだった。
病いと言われれば、それも仕方がない。
自分の好みを注ぎ込んだ女を育てるのは…男としての私の性なのだろう。
私には息子は居るが娘は居ない。
もし血を分けた自分の娘に、この病いが出たら…。
考えるだけで冷や汗ものだ。
私が一代で築いた店は、もう息子に譲り気楽な隠居生活となり。
日々の老いと付き合いながら吉原に通う。
そんな時に手に入れたのが、手鞠なのだ。
手鞠はすぐに私に懐いた。
どうやら私に、故郷の祖父を重ねてるようだった。
膝の上に乗せてやったら無邪気に喜び。
そこは手鞠の指定席となったのだ。
私は彼女に、名前と共に日課を与えた。
少しずつ胸が膨らみ始め、しかしまだ無毛の恥丘のうちに出来る事を。
毎夜就寝前に、自分の乳首とさね豆を弄ぶようにと。
全裸になり姿見に映しながら、である。
最初はその行為に何の意味があるのか、きっと解らないであろうが。
日々を重ねていくうちに、徐々に変化していく。
処女の乳首とさね豆は、毎夜の刺激に感度と膨らみを増していき。
身体の奥で何とも言えない感覚が湧き上がり言葉にならない吐息が唇から漏れてくる。
姿見に映る己の姿を見て、動悸が跳ねて弄る手が止まらずに…。
どうしようもなく言い難い感覚が、脳天に突き抜けたら我慢せずに声をあげて。
そうやって逝き果てて眠りにつくのだ。
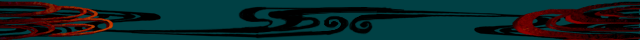
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える