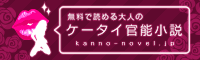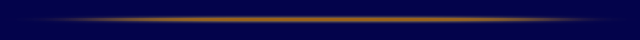
胡蝶の夢~私の最愛~⑪【夢路・ゆめじ】
第7章 溶けてゆく心
「そのようなご自分を貶めるおっしゃりようはお止め下さいませ。殿、泉水は殿をお信じ申し上げております。たとえ世の人が何と申そうと、殿が本当はお優しく勇気のあるお方と信じております。現に、殿のご聡明さを知る者たちも少なくはございません。嫁ぐ前、私は殿が家臣たちにも情をお示しになる、英明な賢君であるというお話をお聞き致しました」
泰雅についての風評は様々だ。稀代の好色家、名うての遊び人だと言う者もあれば、いや、あれはなかなかの切れ者で侮れぬと評する者もいる。一体、そのどちらが真の泰雅なのかを知る者は榊原家の重臣たちの中にも実はいないのだった。
こんな逸話がある。父 が逝去して十二歳で家督を継いでまもない頃、泰雅の近習が家宝の壺を割った。大の大人でも一人では持ち上げられぬほどの大きさで、ギヤマン細工に美しい切り子模様が施されていた。何でも初代将軍東照公家康が九州の島津家より献上を受けた逸品であり、それをそのまま榊原家の初代当主泰(やす)瑛(てる)に下賜したものだという。泰瑛は三河以来の譜代の重臣の一人であった。
以来、榊原家ではその壺を家宝として歴代当主は大切に引き継いできた。その品を、泰雅の近習の少年が割ってしまったのだ。丁度、その日は蔵から収蔵品を出し、虫干しをすることになっていた。初代将軍から賜った大切な至宝は蔵の奥深くにしまい込まれ、厳重に守られているのだ。
壺を二人がかりで運び出す際、一方の少年が誤って手を滑らせてしまったのだ。事は重大であった。一体、その少年の処分をどうするのか、老臣たちは顔を見合わせた。が、泰雅はこともなげに言った。
―壺を割ったのは是近ではない。俺が割ったのだ。俺が滅多に見られぬ家宝の壺をいじくり回していて、割った。あの壺が割れたのは、俺のせいだ。そういうことにせよ。
そのひと声で、近習の少年は何のお咎めもなく終わった。公方さまには、泰雅が直々に登城し事の次第を述べ、平伏してお詫びを言上し、それで事なきを得た。
当時、十五歳であった飯田是近は今では泰雅の信頼厚い側近として榊原家でも重きをなしている。
泰雅についての風評は様々だ。稀代の好色家、名うての遊び人だと言う者もあれば、いや、あれはなかなかの切れ者で侮れぬと評する者もいる。一体、そのどちらが真の泰雅なのかを知る者は榊原家の重臣たちの中にも実はいないのだった。
こんな逸話がある。父 が逝去して十二歳で家督を継いでまもない頃、泰雅の近習が家宝の壺を割った。大の大人でも一人では持ち上げられぬほどの大きさで、ギヤマン細工に美しい切り子模様が施されていた。何でも初代将軍東照公家康が九州の島津家より献上を受けた逸品であり、それをそのまま榊原家の初代当主泰(やす)瑛(てる)に下賜したものだという。泰瑛は三河以来の譜代の重臣の一人であった。
以来、榊原家ではその壺を家宝として歴代当主は大切に引き継いできた。その品を、泰雅の近習の少年が割ってしまったのだ。丁度、その日は蔵から収蔵品を出し、虫干しをすることになっていた。初代将軍から賜った大切な至宝は蔵の奥深くにしまい込まれ、厳重に守られているのだ。
壺を二人がかりで運び出す際、一方の少年が誤って手を滑らせてしまったのだ。事は重大であった。一体、その少年の処分をどうするのか、老臣たちは顔を見合わせた。が、泰雅はこともなげに言った。
―壺を割ったのは是近ではない。俺が割ったのだ。俺が滅多に見られぬ家宝の壺をいじくり回していて、割った。あの壺が割れたのは、俺のせいだ。そういうことにせよ。
そのひと声で、近習の少年は何のお咎めもなく終わった。公方さまには、泰雅が直々に登城し事の次第を述べ、平伏してお詫びを言上し、それで事なきを得た。
当時、十五歳であった飯田是近は今では泰雅の信頼厚い側近として榊原家でも重きをなしている。
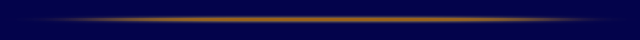
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える