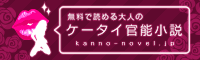経済財政愚問放談 その1
第13章 グローバリズムは必ず飽和する
グローバリズムに限らず、資本主義経済は必ず飽和します
例えば日本国内で考えて見ましょう
昔は日本にも沢山の自動車製造会社が有りました
日産・トヨタ・三菱・マツダ・ホンダ・スズキ・ダイハツ・スバルと現存する会社以外に、日野・いすゞは乗用車も作っていましたし、マイナーな所だと日本軽自動車・オオタ・プリンス・たま・ホープスター・くろがね・アキツ・オリエント等々大小合わせて物凄い数有りました
これ等自動車製造会社が日本国内市場で激しい競争を繰り広げ、市場を拡大して行きました
そして市場拡大が頂点に達した時、販売数が伸び悩み始めました
製品が市場に行き渡り、購買力が限界に達したのです
これが資本主義経済の飽和現象です
市場のパイがある程度決まっている以上、必ず購買力が限界に達し市場が飽和状態に成ります
買い換え需要は勿論有りますが、一度限界に達した段階で景気が後退局面に入る為、市場が縮小して行きます
ここで市場原理に乗っ取り、体力の無い会社が淘汰されて行きます
そして更に購買力を失った失業者が増える為、市場はもっと縮小します
売れなくなった商品を売る為、企業が価格をさげて来ます
するとコスト削減が始まります
そしてその企業に納入していた企業も収益が減ります
そうすると当然労働者の収入が減ります
はい、デフレスパイラルの誕生です
此処まで行く前に、政府が財政出動を増やしたり、公共投資で需要創出したりして、少なくても1997年代迄は日本は何とかデフレスパイラルには陥りませんでした
そう、消費税増税が行われた為にデフレスパイラルが深刻化したのです
あの当時は小渕内閣の所得税減税で景気が回復局面に入り掛けて居ましたが、次の橋本龍太郎内閣で今だ道中場の景気回復を消費税増税で台無しにしたのです
はて?2014年にも似たような事が?
まぁ、それはさて置き、資本主義経済は市場の飽和から景気後退、其処からの景気回復を繰り返す構造に有る訳です
では、もう少し突っ込んだ論考を致しましょう
国内で市場の飽和が始まった資本主義国家が何を始めるか?
勿論対外輸出です
初めは国内工場で生産した商品を、海外市場に輸出します
しかし、海外市場もいずれ限界に達します
何せ輸出相手国にも、自国の産業が有る訳ですから
例えば日本国内で考えて見ましょう
昔は日本にも沢山の自動車製造会社が有りました
日産・トヨタ・三菱・マツダ・ホンダ・スズキ・ダイハツ・スバルと現存する会社以外に、日野・いすゞは乗用車も作っていましたし、マイナーな所だと日本軽自動車・オオタ・プリンス・たま・ホープスター・くろがね・アキツ・オリエント等々大小合わせて物凄い数有りました
これ等自動車製造会社が日本国内市場で激しい競争を繰り広げ、市場を拡大して行きました
そして市場拡大が頂点に達した時、販売数が伸び悩み始めました
製品が市場に行き渡り、購買力が限界に達したのです
これが資本主義経済の飽和現象です
市場のパイがある程度決まっている以上、必ず購買力が限界に達し市場が飽和状態に成ります
買い換え需要は勿論有りますが、一度限界に達した段階で景気が後退局面に入る為、市場が縮小して行きます
ここで市場原理に乗っ取り、体力の無い会社が淘汰されて行きます
そして更に購買力を失った失業者が増える為、市場はもっと縮小します
売れなくなった商品を売る為、企業が価格をさげて来ます
するとコスト削減が始まります
そしてその企業に納入していた企業も収益が減ります
そうすると当然労働者の収入が減ります
はい、デフレスパイラルの誕生です
此処まで行く前に、政府が財政出動を増やしたり、公共投資で需要創出したりして、少なくても1997年代迄は日本は何とかデフレスパイラルには陥りませんでした
そう、消費税増税が行われた為にデフレスパイラルが深刻化したのです
あの当時は小渕内閣の所得税減税で景気が回復局面に入り掛けて居ましたが、次の橋本龍太郎内閣で今だ道中場の景気回復を消費税増税で台無しにしたのです
はて?2014年にも似たような事が?
まぁ、それはさて置き、資本主義経済は市場の飽和から景気後退、其処からの景気回復を繰り返す構造に有る訳です
では、もう少し突っ込んだ論考を致しましょう
国内で市場の飽和が始まった資本主義国家が何を始めるか?
勿論対外輸出です
初めは国内工場で生産した商品を、海外市場に輸出します
しかし、海外市場もいずれ限界に達します
何せ輸出相手国にも、自国の産業が有る訳ですから

 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える