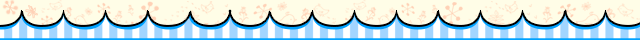
イチャコラミックス
第6章 盛夏に聞こえる鳴き声
「由芽、好きだ…由芽。」
「わたし…もっ…」
好きだ。
一度と言っていたのはどの口だろうか。
アブラゼミの声がいつの間にかヒグラシに変わっていた。
「ぁ、あ…」
晴一は由芽の下腹に手の平を当てた。
キラキラ光が溢れ出て、暖かくて、由芽はそれだけで心地よくなった。
もう片方の手で、膣から出てくる白い塊を掬い上げる。
白い塊はクルクル回ると光になって空気に消えた。
「大丈夫か?」
「…もちろん。もっとしたいくらい。」
「ん…」
晴一は由芽にそっと口付けた。
「泊まって行けよ。明日も休みだろ?」
「いいの?」
「家に電話しとく。」
「…実は、泊まるって言ってあるんだよね。」
「え、ここに?」
「お父さんは半分怒ってたけど、ほら、ウチの両親も同じだから。」
由芽の両親も、学生と教師という関係だった。
父親は生徒に手を出した(実際気持ちしか出してないけど)責任を取るため教師を辞めた。ま、ちょうど応募した小説が入賞し、小説家になれたという理由もあるけど。
「それに先生ならいいって。凄いよ、晴一さんへの信頼が。」
「ええ…。」
信頼と聞き、晴一は頭を抱えた。
その信頼を裏切るような行為を家に招き入れてから今までしていたから。
「いつくるの?って。」
「挨拶ならこの間。」
自宅におじゃまし、お付き合いさせていただきたい旨を伝え頭を下げたのはこの春。卒業後すぐの事だ。
「お父さんもお母さんも遊びにおいでって。弟も会いたがってるよ。」
「え、あぁ、そうか。ありがたいなぁ、それは。」
「でもお父さんは話を聞いて小説のネタにしようとしているのかも。」
「あー、なるほど。」
お邪魔した時、両親が海外で医療従事していた話に興味を持っていたっけ。二人は弟のソラトが出来て帰国し、今は市内の病院で働いている。ソラトは五十手前の高齢出産だったが、母親が産科医だったこともあり、無事に元気に生まれた。…どうしてるかな。毎日顔を見ているから見れない日が続くと寂しい。
二十三歳の年の差なんてほぼ親子同然とも言える。晴一にとってソラトとの日々は父親になる練習でもあった。
いつか。
「電話するよ。」
「そう?」
「ずっと一緒にいたいからな。」
晴一はそう言うと、肌をしっとりさせた恋人を抱き寄せた。
「風呂入ったら夕飯にしよう。」
「うん!」
由芽は元気に返事をすると晴一の背中に腕を回した。
「わたし…もっ…」
好きだ。
一度と言っていたのはどの口だろうか。
アブラゼミの声がいつの間にかヒグラシに変わっていた。
「ぁ、あ…」
晴一は由芽の下腹に手の平を当てた。
キラキラ光が溢れ出て、暖かくて、由芽はそれだけで心地よくなった。
もう片方の手で、膣から出てくる白い塊を掬い上げる。
白い塊はクルクル回ると光になって空気に消えた。
「大丈夫か?」
「…もちろん。もっとしたいくらい。」
「ん…」
晴一は由芽にそっと口付けた。
「泊まって行けよ。明日も休みだろ?」
「いいの?」
「家に電話しとく。」
「…実は、泊まるって言ってあるんだよね。」
「え、ここに?」
「お父さんは半分怒ってたけど、ほら、ウチの両親も同じだから。」
由芽の両親も、学生と教師という関係だった。
父親は生徒に手を出した(実際気持ちしか出してないけど)責任を取るため教師を辞めた。ま、ちょうど応募した小説が入賞し、小説家になれたという理由もあるけど。
「それに先生ならいいって。凄いよ、晴一さんへの信頼が。」
「ええ…。」
信頼と聞き、晴一は頭を抱えた。
その信頼を裏切るような行為を家に招き入れてから今までしていたから。
「いつくるの?って。」
「挨拶ならこの間。」
自宅におじゃまし、お付き合いさせていただきたい旨を伝え頭を下げたのはこの春。卒業後すぐの事だ。
「お父さんもお母さんも遊びにおいでって。弟も会いたがってるよ。」
「え、あぁ、そうか。ありがたいなぁ、それは。」
「でもお父さんは話を聞いて小説のネタにしようとしているのかも。」
「あー、なるほど。」
お邪魔した時、両親が海外で医療従事していた話に興味を持っていたっけ。二人は弟のソラトが出来て帰国し、今は市内の病院で働いている。ソラトは五十手前の高齢出産だったが、母親が産科医だったこともあり、無事に元気に生まれた。…どうしてるかな。毎日顔を見ているから見れない日が続くと寂しい。
二十三歳の年の差なんてほぼ親子同然とも言える。晴一にとってソラトとの日々は父親になる練習でもあった。
いつか。
「電話するよ。」
「そう?」
「ずっと一緒にいたいからな。」
晴一はそう言うと、肌をしっとりさせた恋人を抱き寄せた。
「風呂入ったら夕飯にしよう。」
「うん!」
由芽は元気に返事をすると晴一の背中に腕を回した。
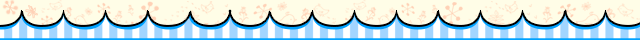
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える