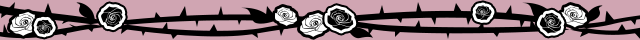
性に溺れる私
第6章 【アブナイ不徳義】
一番聞かれたくない質問……サラッと聞いてくるのは付き合ってるカップルならごく自然なことなんだよね。
今までそんな相手作ってこなかったから正直面食らった。
「あぁ………えっと」
答えに困っていると
「あ、答えたくないならいいよ」って気遣ってくれるのも大樹の優しさ。
「え?お前ら付き合ってんのにそんな話もしてねぇの?やってばっかかよ」
本当デリカシーのない男。
そう思われるのも癪に障るから答えてあげるわよ。
「ごめん、言ってなかったね?うちの親は二人とも医者」
「えっ!?マジ!?」
「そう、お父さんは心臓外科医、お母さんは麻酔科医」
「へぇ〜、だから常に家に居ないんだ?そういう点では一緒か…いやいや、職種のレベルが桁違いだろ!うちはただのホテルスタッフだぞ」
「立派な仕事じゃん」
「お、おう……それで飯食わせてもらってるよ」
「大樹はサラリーマンだっけ?」
「そっ!しがないサラリーマンにパート勤めの母ちゃんだよ」
「いつか会ってみたいな」
「えっ!あ……うん、会ってやって…エヘヘ」
「けっ!仲良くやってろ」
結局私たちは穂高くんの前でイチャついてしまう。
知らない道を歩いて着いた家の前。
縦長のデザイナーズマンション。
コンクリート打ちっぱなしってやつ?
「凄いだろ?これでボンボンとかマジ有り得ねえわ」って大樹が悄気げてる。
ホテルスタッフってかなりの大手だったみたい。
ヨシヨシして大樹を慰める。
「それでも私は大樹を選ぶよ」と耳打ちしたら嬉しそうに笑う。
通された部屋は本当にホテルの一室みたいだった。
「あ、この隣は入らないでね?女の子とヤル部屋だから」
誰も聞いてないわ。
いちいち言わなくていい。
黒、白、グレーで統一された広々とした部屋。
黒いソファーの前にある白のローテーブルで勉強することになった。
「適当だけど」と言ってミネラルウォーターと老舗洋菓子店のマドレーヌの入った菓子入れとか持って来ちゃって笑える。
似合ってないんだもん。
「じゃ、早速ここから教えてくれる?藍沢さん」
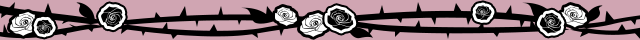
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える