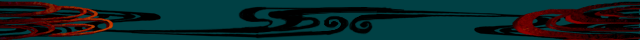
人身供物の村娘
第2章 贄としての生活
菊理は、一緒に食事を囲むことなど、家族ともあまりしてこなかった。
贄に決まるまえも、家が裕福では無いため家族は働きに出ていたし、家のことは菊理が全てこなしていた。
食べるのも独りだった。
だから、誰かと膳を挟んで食事をすることがとても暖かく感じた。
「黒狐様は、好物は鶯豆以外になにかございますか?」
そう聞くと、少し考えた末に黒狐は答えた。
「干し芋だな…あとは、これからは干し柿もうまい…干したものは栄養や甘みが詰まって好きだ。」
そう答える黒狐に、菊理は里の祖父を思い出した。
祖父も同じことを言っていた。
「なぁ、菊理よ。」
黒狐が箸を膳に置き、話し始めた。
「はい。」
そう答えると、黒狐は里に帰りたいか聞いた。
「黒狐様、なんと?」
聞き返すしか無かった。
「贄を貰っていてもな、子をなせる訳では無い、昔、贄をもらっていたのは村への罰だったのだ。
意味の無い狩猟や、伐採などに対して神罰のつもりであった。
だから、時が来たら贄は記憶を消して里に返していた。」
それを聞いた時、菊理はとてもむねがきゅうとなった。
「私では、お役目不足ですか?」
「何もそういうんでない。
帰りたいならここであったことを忘れて、帰るだけだ。
居たいなら居たいだけいて構わぬ。」
そう言い放つ、黒狐様はどこか冷たそうだった。
「私は、居たいです。
ここに居たいです。」
何故?と聞く黒狐に、菊理も箸を膳において真面目に答えた。
「初めはすごく怖かったです。
何をされるかわからぬ土地に来て、急に布団に転がされて。
でも、今は黒狐様が少し楽しく笑う顔も髪の毛を洗う時も大好きなのです。
心地よいのです。」
顔が熱くなるのを実感しながら菊理は答えた。
「面白いやつよの。
大抵はみな、あの髪の毛の時間で帰りたいと言うに。
まぁ良い、勝手にしろ。」
そう言われてなんだかほっとした。
贄に決まるまえも、家が裕福では無いため家族は働きに出ていたし、家のことは菊理が全てこなしていた。
食べるのも独りだった。
だから、誰かと膳を挟んで食事をすることがとても暖かく感じた。
「黒狐様は、好物は鶯豆以外になにかございますか?」
そう聞くと、少し考えた末に黒狐は答えた。
「干し芋だな…あとは、これからは干し柿もうまい…干したものは栄養や甘みが詰まって好きだ。」
そう答える黒狐に、菊理は里の祖父を思い出した。
祖父も同じことを言っていた。
「なぁ、菊理よ。」
黒狐が箸を膳に置き、話し始めた。
「はい。」
そう答えると、黒狐は里に帰りたいか聞いた。
「黒狐様、なんと?」
聞き返すしか無かった。
「贄を貰っていてもな、子をなせる訳では無い、昔、贄をもらっていたのは村への罰だったのだ。
意味の無い狩猟や、伐採などに対して神罰のつもりであった。
だから、時が来たら贄は記憶を消して里に返していた。」
それを聞いた時、菊理はとてもむねがきゅうとなった。
「私では、お役目不足ですか?」
「何もそういうんでない。
帰りたいならここであったことを忘れて、帰るだけだ。
居たいなら居たいだけいて構わぬ。」
そう言い放つ、黒狐様はどこか冷たそうだった。
「私は、居たいです。
ここに居たいです。」
何故?と聞く黒狐に、菊理も箸を膳において真面目に答えた。
「初めはすごく怖かったです。
何をされるかわからぬ土地に来て、急に布団に転がされて。
でも、今は黒狐様が少し楽しく笑う顔も髪の毛を洗う時も大好きなのです。
心地よいのです。」
顔が熱くなるのを実感しながら菊理は答えた。
「面白いやつよの。
大抵はみな、あの髪の毛の時間で帰りたいと言うに。
まぁ良い、勝手にしろ。」
そう言われてなんだかほっとした。
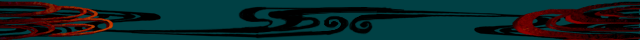
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える